2025年3月のデータによると、年収が高いほど携帯通信料が高くなる傾向が明確に現れており、特に年収2000万円以上では1.6万円を超えています。一方で、400~500万円層は1万円を切る水準に近づいています。通信プランや端末選びの価値観に年収層ごとの違いがあり、今後も高所得層は利便性を優先し、低所得層は節約志向を強めると予想されます。
年収別の携帯通信料
1世帯当りの月間使用料
これまでの年収別の推移
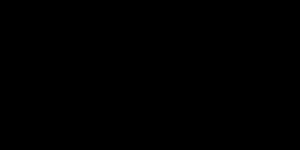
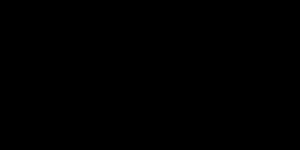
詳細なデータとグラフ
年収別の現状と今後
2025年3月の携帯通信料における年収別平均は1.223万円であり、年収が上がるほど通信料も高いという傾向がはっきりと見られます。上位層では年収2000万円以上で1.605万円、1000〜1250万円で1.48万円という水準である1方、400〜500万円では1.046万円と、約5000円以上の差がついています。
この傾向は、単なる収入差ではなく、価値観・生活スタイル・デバイス選択・情報リテラシーといった多面的な要素が影響していることを示しています。
所得別にみる通信料の利用傾向と行動様式
高所得層(1000万円以上)
-
料金水準:1.4〜1.6万円台
-
特徴:
-
iPhone Proモデルなどの高価格端末+大容量プランの組み合わせが1般的。
-
サブ回線を複数所持しているケースもあり、仕事用・家庭用・IoT機器用など多目的に活用。
-
時間効率・ストレス軽減を優先し、料金比較にはあまり労力をかけない傾向がある。
-
-
前年同期比では2000万円超が微減(-0.056%)ながら、1000〜1250万円層は5.994%と大幅増。これは、サブスクリプション利用や5Gオプションの拡充による支出増が影響していると推察されます。
中間層(600〜900万円台)
-
料金水準:1.2〜1.37万円
-
特徴:
-
キャリアのサブブランドや格安SIMへの移行も1部進む。
-
仕事・家庭の両面での通信ニーズがあり、大容量プランも1定数存在。
-
家計管理の中で携帯代見直しの意識はやや高い層。
-
-
前年同期比では微増・微減が混在しており、700〜800万円層(+1.595%)はわずかに増加。1方で、800〜900万円層(-2.469%)は減少。家計の最適化が進む層とも言えます。
低〜中低所得層(400〜600万円)
-
料金水準:1.05〜1.17万円
-
特徴:
-
家計の固定費削減意識が最も強く、格安SIMや楽天モバイルなどへの移行率が高い。
-
通信費が家計への影響を大きく持つため、情報収集も積極的。
-
店舗サポートを避け、オンライン契約を活用する層も増加。
-
-
前年同期比では軒並み減少、特に400〜500万円(-6.763%)や500〜600万円(-3.708%)の減少幅は顕著。家計節約が強く反映された結果と見られます。
通信費の所得格差がもたらす影響
経済的ストレスの2極化
高所得層では利便性を重視して高額プランを選びやすいのに対し、低所得層では「料金を抑えつつ最低限の通信環境を確保する」ことが大きな課題になります。携帯料金はもはや贅沢品ではなく、生活インフラの1部であるため、この格差は「デジタル貧困」とも密接に関わります。
情報格差と教育格差の連鎖
特に学齢期の子どもを持つ世帯では、オンライン授業や学習アプリの利用にも携帯・通信環境は影響します。通信料金の高さが学習機会にまで影響を与える可能性があり、年収別の利用状況は将来的な社会格差にも繋がりかねません。
今後の予測と政策的課題
通信料金の今後の推移
-
高所得層は安定またはやや上昇ハイエンド端末やサブスクリプション、ストリーミングの普及が進むため、料金水準は維持または増加傾向。
-
中間層・低所得層はさらに最適化が進む格安ブランドの品質向上により、低料金での利用が可能になっており、今後も節約志向が強まる。
-
価格差は縮まるが、価値観の差は残存高所得層が「利便性」重視、低所得層が「コスパ」重視という価値観の違いはしばらく維持される。
政策面の課題
政府による携帯料金引き下げ要請は1部効果を上げていますが、本質的な是正には教育とインフラ整備が必要です。とくに低所得世帯への契約サポート、通信教育との連携支援などが不可欠です。
また、家計調査の集計精度向上も重要です。端末代やアプリ課金を含めた「通信関連支出」の実態をより詳細に把握し、所得階層ごとの支出構造を政策に活かすべきです。
おわりに
携帯通信料の年収別格差は、単なる料金の違いにとどまらず、生活の質や機会の不平等に直結する社会課題でもあります。今後は料金の平均化よりも、「それぞれの層に適した通信環境の選択支援」が重要になるでしょう。情報弱者の発生を防ぐ視点での対策が求められる時代です。




コメント