国内パック旅行費は年収に比例して支出額が上昇する傾向があり、特に1250~1500万円層の支出が急増しています。物価高の影響や富裕層の旅行志向が背景にあり、中間層以下は支出を抑制。高所得層のレジャー回帰と対照的に、低・中所得層は節約志向が継続しています。今後は高所得層中心の旅行市場構造が進み、観光産業の二極化が懸念されます。
年収別のパック旅行費(国内)
1世帯当りの月間使用料
これまでの年収別の推移
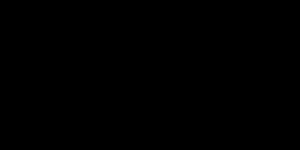
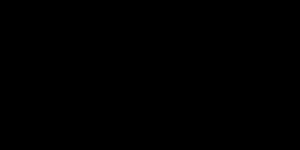
詳細なデータとグラフ
年収別の現状と今後
年収別のパック旅行費は、当然ながら収入が上がるほど支出額も大きくなる傾向にありますが、今回の最新データでは、それ以上に大きな「支出意欲の格差」も浮き彫りになりました。1250万〜1500万円層が6810円と全体平均の2.6倍以上を支出しており、前年同期比で+193.3%という急伸を記録。これに対し、500〜600万円層は1427円で-49.56%と大幅に減少しており、年収階層間のレジャー消費における分断が鮮明です。
この格差は、単なる可処分所得の違いにとどまらず、物価上昇下での「旅行を優先する層」と「旅行を削る層」の分かれ目としても機能しています。
パック旅行を牽引する高所得層の動き
高所得層、とりわけ1250〜1500万円層や1000万円超の層で支出が急増している背景には、コロナ禍による海外旅行の制限が国内旅行需要へと転化されたことが挙げられます。また、物価上昇に対する購買耐性も高く、割高感があっても旅行を継続・増加させる傾向が顕著です。
この層では、価格よりも「質」や「利便性」が重視されるため、パック旅行の中でもハイクラス商品やラグジュアリーな宿泊施設を含むプランが好まれていると考えられます。
中低所得層の旅行費用の抑制と不安
1方で、500〜600万円層や300〜400万円層など中間以下の年収層では、旅行支出の減少が目立ちます。特に500〜600万円層では前年比-49.56%と、コストカットの影響が色濃く出ており、物価高や住宅ローン、教育費などの固定支出の増加により、旅行は「削る対象」になっていることが示唆されます。
また、この層ではパック旅行よりも「個別手配による節約旅行」や「近場への日帰り旅」などへのシフトも考えられ、パック商品の魅力が低下している可能性もあります。
所得階層によるレジャー2極化の進行
2020年代以降、日本では「レジャーの2極化」が進んでおり、旅行・外食・趣味消費などで高所得層とそれ以外の層で行動が大きく乖離しています。パック旅行費においてもこの傾向は如実で、特定の富裕層が高価格帯商品を支える1方で、裾野を形成していた中間層が離脱しつつあります。
このような動向は観光業界にとっても課題であり、ターゲットの再定義や「手の届く贅沢」といった新たなパッケージ開発が求められるでしょう。
今後の展望と政策的示唆
今後のパック旅行費の年収別動向を予測すると、以下のような方向性が考えられます:
-
高所得層の支出拡大継続 引き続き富裕層をターゲットとした「上質な国内旅行」の需要は堅調であり、地域観光資源の高付加価値化が重要となる。
-
中低所得層への支援政策の必要性 観光庁や地方自治体による割引キャンペーンや、交通費補助制度などを通じて、旅行に手が届かない層の支出喚起が求められる。
-
パッケージ商品の多様化 従来の「全込み型」から、柔軟にカスタマイズできる「半パッケージ型」など、価格感度が高い層にも選ばれる工夫が必要となる。
おわりに
パック旅行は、国内観光にとって重要な市場であり続けていますが、年収別に見るとその構造は大きく変化しています。富裕層の活発な支出に支えられつつある1方で、格差の拡大が「旅行する層」と「しない層」を明確に分け始めています。観光産業はこの動向を注視し、包摂的な発展を目指す必要があります。




コメント