2020年11月から2025年3月の家計調査によると、持家世帯の平均畳数は全国平均で38.6畳。地方都市では広い住宅が多く、新潟市や山形市、長野市などは45畳前後。一方、東京都区部や那覇市では30畳台前半と都市部での住空間の狭さが目立つ。都市部では土地価格の高騰やマンション志向、世帯構成の変化が影響。今後は高齢化、単身世帯の増加、地方移住の流れにより、広さより利便性や省エネ性を重視した住宅志向が進展する見込み。
平均畳数(持家)の家計調査結果
平均畳数(持家)の多い都市
平均畳数(持家)の少ない都市
これまでの平均畳数(持家)の推移
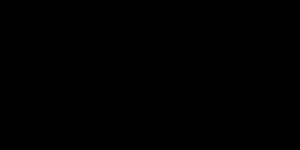
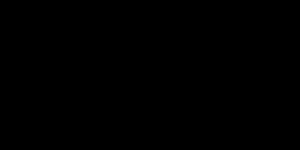
詳細なデータとグラフ
平均畳数(持家)の現状と今後
家計調査の結果によると、2025年3月時点での全国の持家世帯の平均畳数は38.6畳。これは6畳換算で6.4部屋分ほどに相当し、日本人が想像する「1般的な1戸建て住宅」とほぼ1致する広さである。
この中で、新潟市(45.1畳)や山形市(45畳)、長野市(44.7畳)などの地方中核都市は軒並み40畳台後半のゆとりある住宅が目立つ。1方で、東京都区部(32.9畳)、那覇市(33.2畳)など都市部や人口密度の高い地域では30畳台前半と、住宅の狭小化が顕著となっている。
畳数の地域差を生む要因
地域ごとの住宅の広さには以下のような背景がある:
-
土地価格の違い:都市部ほど土地価格が高く、面積を抑えた住宅や集合住宅が多くなる。
-
戸建とマンションの比率:地方都市では戸建が主流だが、都市部ではマンション比率が高く、間取りが制限されやすい。
-
持家取得の年齢層:地方では30〜40代で戸建てを建てる傾向が強く、広めの設計が選ばれやすい。
-
気候と文化的背景:雪国や寒冷地では居住スペースにゆとりを持たせる設計が好まれ、暖房効率を考慮した間取りが多い。
都市部の狭小化と世代交代の影響
都市部で平均畳数が減少傾向にある背景には、以下のような社会変化がある。
-
核家族化・単身世帯の増加:東京都区部や政令市では単身者・夫婦のみの世帯が主流となり、広い住宅の必要性が薄れている。
-
高齢化によるダウンサイジング:子育てを終えた世代が、老後の利便性や維持管理の簡便さを理由に、広い戸建からコンパクトな住居へ移行する動きも。
-
集合住宅の増加:都市部では新築物件の大半が分譲・賃貸マンションであり、1戸あたりの専有面積が限定される傾向が強い。
地方都市における広さ維持と住宅環境の余裕
地方都市では依然として40畳台以上の広い住居が珍しくない。その要因は以下の通り。
-
地価の安定と土地取得の容易さ:新潟、山形、長野などは郊外でも利便性があり、広い敷地で住宅を建てやすい。
-
3世代同居や親族との近居:地方では複数世代が同居する文化が残りやすく、部屋数や広さが求められる。
-
生活スタイルの維持:農作業スペースや収納空間、客間などが必要とされ、広い間取りが望まれる。
変動するトレンドと今後の見通し
今後の住宅面積のトレンドは、以下の3つの方向性が考えられる。
-
利便性重視の都市型住宅の増加 狭くても駅近やスーパー併設などの利便性を優先する選好が進む。特に若年層や高齢者層で顕著。
-
地方回帰と広い住宅の再評価 テレワークの浸透や地方移住の促進により、ゆとりある広さと自然環境を兼ね備えた住宅の需要が再燃する可能性がある。
-
エネルギー効率・環境性能の重視 住宅広さよりも省エネ性能や断熱性など、「快適性の質」が選ばれる指標へと変化していく。
まとめ
持家における平均畳数のデータは、日本社会の変化、都市構造の特性、そして住宅に対する価値観の違いを色濃く反映している。今後の日本社会では、「狭くても快適・機能的」「広くて多用途」といった2極化が進む1方で、それぞれの生活スタイルに合った柔軟な住宅の提供が求められるようになるだろう。




コメント