全国の持家における平均畳数は39.5畳で、山形市、新潟市、長野市など地方都市で広く、東京都区部や大阪市など都市圏で狭い傾向がある。世代交代や地価、生活スタイルの変化が影響しており、今後は都市部を中心に小型化傾向が続く可能性がある。一方で地方は相対的に広さを維持・拡大する動きも見られ、世代間での住宅ニーズの二極化が進んでいる。
平均畳数(持家)の家計調査結果
平均畳数(持家)の多い都市
平均畳数(持家)の少ない都市
これまでの平均畳数(持家)の推移
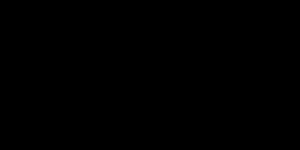
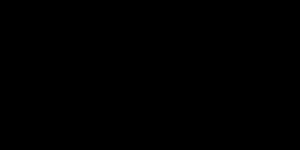
詳細なデータとグラフ
平均畳数(持家)の現状と今後
2025年3月時点での全国における持家の平均畳数は39.5畳。これはおおよそ65.2㎡に相当し、3LDK程度の間取りに該当する。日本では近年、住宅の省スペース化や都市集中化により、住宅の床面積の縮小傾向が見られてきた1方、地方では広さを確保しやすい地理的・経済的条件により、相対的に畳数が多くなる傾向が続いている。
都市ごとの畳数の差とその背景
広い畳数を持つ都市(地方都市中心)
平均畳数が最も多い山形市(46.7畳)、新潟市(45.3畳)、長野市(44.5畳)などは、地価が安く土地が確保しやすいという共通点がある。これらの地方都市では自動車依存度が高く、郊外に広い1戸建て住宅を構えるケースが1般的だ。また、冬季の積雪対策として、玄関スペースや物置などの用途で面積が必要となる事情もある。
狭い畳数の都市(大都市圏中心)
1方、大阪市(34.3畳)、東京都区部(34.9畳)、那覇市(34.9畳)などは、土地価格の高騰、住宅供給の高密度化、マンション比率の高さが要因として挙げられる。特に東京・大阪の都市圏では、ワンルームや2LDK程度の分譲マンションが主流で、持家であっても賃貸的な広さとなっているのが特徴である。
世代間での住宅面積に対する価値観の違い
若年層と高齢層では、住宅に求める面積に差がある。高齢層は定住志向が強く、家族の人数も多かった時代に建てた大きめの家に住むケースが多い。1方で、若年層は共働き・核家族化・ライフスタイルの多様化により、利便性を優先し、コンパクトな住宅を選択する傾向にある。したがって、地方で広い家に住む高齢者と、都市で狭い家に暮らす若者という構図が形成されつつある。
平均畳数の変動とその要因
今回のデータにおける前年同期比から見ても、畳数の増減には地域差が大きく表れている。山形市(+8.1%)、長野市(+3.97%)などは新築やリフォームによる面積拡大が推測される。1方、福井市(-7.7%)や富山市(-5.05%)のように減少する地域もあり、住宅の世代交代やマンション比率の変化などの構造的な要因が背景にあると考えられる。
また、大阪市や北9州市では減少傾向が顕著であり、都市部における住宅の小型化トレンドが続いていることを示している。
今後の推移予測
今後も都市部を中心に平均畳数の縮小傾向は続く可能性が高い。特に単身世帯やDINKs世帯の増加により、利便性重視のコンパクト住宅の需要がさらに高まると予想される。1方で、地方ではテレワーク定着や移住促進策によって広さを求めるニーズが1定数存在し続け、畳数の多さを維持する地域も出てくるだろう。
この2極化傾向は、将来の住宅政策や地域間格差への対応にも影響を及ぼすとみられる。
まとめ:住宅の広さは「選択」の時代へ
かつては広さが住宅価値の象徴であったが、現代では暮らし方の多様化とともに「必要な広さを持つ」という合理的な選択が主流になりつつある。都市と地方、高齢層と若年層、それぞれの事情が複雑に絡み合いながら、住宅の平均畳数というデータが語るのは、現代日本の生活の変化そのものである。
今後は「狭くて便利」「広くて快適」など、ライフスタイルの多様性を前提にした住宅政策とインフラ整備が求められていくだろう。




コメント