2025年3月時点の家計調査によると、勤労世帯の65歳以上人員数は全国平均0.3人。長野市や津市、神戸市など高齢層の同居率が高い都市と、松山市や堺市のように低い都市で大きな差がある。地域性、世代交代、就労や扶養意識の変化が背景にある。今後、世帯構成や地方移住、単身高齢者の増加とともに、新たな課題が顕在化する可能性がある。
65歳以上人員数の家計調査結果
65歳以上人員数の多い都市
65歳以上人員数の少ない都市
これまでの65歳以上人員数の推移
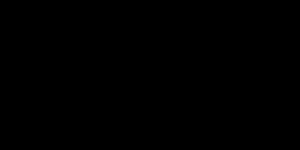
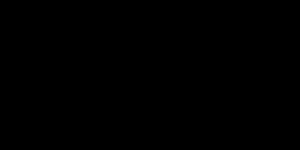
詳細なデータとグラフ
65歳以上人員数の現状と今後
2025年3月時点の家計調査によれば、全国の「勤労世帯」における1世帯あたりの65歳以上人員数は0.3人となっており、これは多くの世帯に高齢者が含まれないか、含まれていても1人以下であることを示しています。つまり、定年後も同居を選ぶかどうかは家庭の事情に大きく依存しており、また高齢者自身の生活の自立度や居住形態の多様化が進んでいることも反映しています。
高齢者同居率が高い都市の特徴
上位都市の背景
-
長野市(0.61人):高齢者人口の割合が全国的にも高く、地元就職や定住志向が強いため、親と子が同居する家族構成が残っている可能性が高い。
-
津市(0.48人)、神戸市(0.47人):地方中核都市でありながら、親世代との同居を継続する文化的背景がある。特に津市の前年比+118.2%という急増は、世代交代や雇用事情の変化による1時的な影響も考えられます。
-
佐賀市、福井市、岡山市、甲府市など:中小都市ながら、扶養意識や地縁が比較的強く残る地域。
急増の理由
多くの都市で前年比40~100%以上の増加が見られる背景には、以下の要因が考えられます:
-
退職後の親が都市部に住む子と同居を始めた
-
子世帯の生活防衛意識により同居が経済的合理性を持つようになった
-
コロナ禍以降の親世帯の孤立回避や介護を前提とした世帯再編
高齢者同居率が低い都市の傾向
下位都市の特徴
-
松山市(0.09人)、堺市(0.1人):都市化が進み、核家族化が根付いている。地元志向が薄く、高齢者は別居または施設入居が1般的。
-
仙台市、川崎市、さいたま市:大都市圏では子世帯の仕事や生活に高齢者を同居させる余地が少なく、むしろ別居での生活支援や訪問介護に依存する傾向が強い。
-
鹿児島市(0.16人):高齢化率が高いにもかかわらず同居率が低いのは、地域として高齢者の自立意識が強い可能性。
同居率の減少理由
-
高齢者の単身・夫婦世帯志向
-
持ち家比率の高さによる「親の持ち家に住み続ける」パターン
-
若年層の都市転出による「老老別居」状態の拡大
-
高齢者施設の地域整備による非同居化
世代間の価値観と高齢者同居の変化
高齢者と同居することの意味合いは、戦後日本の高度経済成長期と比べて大きく変わりました。
-
昔は「家族内労働力」としての存在意義があった高齢者も、現在では扶養コストとみなされることもある。
-
子世帯は共働きが当たり前となり、親世代との生活リズムや介護負担を敬遠する傾向が強まっている。
-
1方で、高齢者の側も年金や貯蓄で自立しようとする意識が強く、「1人で生きる」ことが理想とされつつあります。
今後の推移と地域間格差の広がり
高齢者の単独化・施設化の進行
-
医療と介護の地域包括ケアが整うにつれ、高齢者は単独世帯化・施設依存化していく傾向がさらに進むでしょう。
-
特に都市部では同居が物理的・経済的に難しく、今後も1世帯あたりの65歳以上人員数は減少傾向に向かう可能性があります。
地方での「逆転現象」も
1方、地方では子世帯の出戻りやUターン就職、地方移住の増加によって、高齢者と再同居するケースが増える可能性もあるため、都市部との逆転現象が起きることもあり得ます。
政策と地域社会が果たす役割
-
地方自治体は、同居や多世代居住を支援する住宅政策や補助制度を強化することで、地域の「老いる家族」への対応が問われます。
-
また、親世代の介護と子世代の就労支援を両立させるための地域ケア人材の確保や訪問サービスの拡充が重要になります。
-
同居そのものが目的ではなく、多様な世帯形態に応じた安心な暮らしを実現する柔軟な社会設計が求められています。
まとめ
65歳以上人員数の推移は、単なる高齢者人口の動きだけでなく、世帯構造や地域文化、経済状況、さらには親子関係の在り方までも映し出す鏡です。これからの日本社会においては、「どこで、誰と、どう老いるか」が、都市政策にも家族のあり方にも大きな影響を与える鍵となるでしょう。




コメント