2025年3月時点で女性配偶者の有業率は全国平均42.1%。金沢市(58.3%)や山形市、広島市など地方中核都市では上昇傾向が強く、一方で横浜市(28.7%)など都市部では低下も見られ、地域間格差が拡大している。有業率の増減には地場産業の性質、育児支援政策、通勤環境、文化的要因が複雑に絡む。今後は高齢化や労働力不足を背景に、地域政策や企業の柔軟な雇用制度が鍵となる。
女性配偶者の有業率の家計調査結果
女性配偶者の有業率の多い都市
女性配偶者の有業率の少ない都市
これまでの女性配偶者の有業率の推移
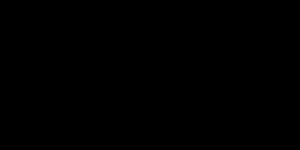
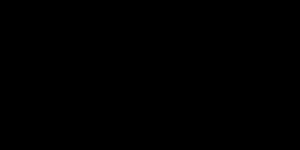
詳細なデータとグラフ
女性配偶者の有業率の現状と今後
家計調査によると、2008年から2025年までの間で女性配偶者の有業率は概ね上昇傾向にある。これは以下のような社会的背景によるものである。
-
共働き志向の高まり:経済的理由だけでなく、自己実現やキャリア継続を重視する女性が増加。
-
少子高齢化による労働力不足:女性の労働3加が期待され、政策的にも後押し。
-
育児・介護支援制度の充実:保育園整備、育児休業制度などが整備されたことで就業継続が可能に。
ただし、その推移には地域差があり、都市構造や地域文化、地場産業の影響が色濃く反映されている。
有業率の高い都市の特徴
2025年3月時点で有業率が特に高い都市には以下のような共通点が見られる。
地方中核都市の存在感
-
金沢市(58.3%)、山形市(53.4%)、広島市(53.2%)などは、地方において経済・行政の中心を担う都市。
-
労働市場が比較的広く、女性向けの雇用(医療・福祉、教育、事務職など)も多い。
地場産業と柔軟な雇用形態
-
パートタイムや短時間勤務など、多様な雇用形態が選べる職場が多く、家庭との両立が可能。
増加率の顕著な伸び
-
特に広島市(+38.18%)、山形市(+31.53%)、金沢市(+25.11%)などは直近1年で大きな伸びを見せており、地域の雇用改善や政策効果がうかがえる。
有業率の低い都市の特徴
1方で、以下のような都市では有業率が低く、前年からの大幅な減少も確認されている。
大都市の課題
-
横浜市(28.7%)や那覇市(31.5%)などは交通混雑や通勤時間の長さ、保育所不足といった都市特有のハードルがある。
-
地価・生活費の高さにより、「働いても損」になると感じるケースもある。
雇用のミスマッチ
-
大都市では専門性の高い職が多く、ブランクのある主婦が再就職しにくい環境も背景にある。
文化的背景
-
特に長崎市や宮崎市のような地域では、「専業主婦」志向が根強く残る傾向もある。
世代間の就業観の変化
世代によっても有業率の差が生まれている。
-
団塊ジュニア世代(40代後半~50代前半):子育てが1段落し、再就職を目指す傾向がある。
-
若年層(30代前半):キャリアと育児の両立を模索しており、育児制度の影響を大きく受ける。
-
高齢層(60代以降):配偶者が引退し家計収入が減ることで、自らも就労するケースが増えている。
今後の見通しと課題
有業率の更なる上昇は見込めるか?
-
労働力人口の維持のため、女性の労働3加は不可避。特に地方自治体や企業のサポート強化が進めば、有業率は今後も上昇傾向となるだろう。
政策課題
-
保育施設の整備や職場での柔軟な勤務制度の導入が依然として重要。
-
中高年女性のスキル習得支援(リスキリング)も今後の焦点となる。
地域間格差の縮小に向けて
-
地方での支援政策が奏功する1方、大都市での低迷が顕著。都市部での雇用・育児両立支援強化が急務である。
まとめ
女性配偶者の有業率は、経済・社会・文化の複雑な要因の交差点に位置しており、単純な「働く・働かない」という2択では語れない現実がある。1人ひとりが多様な選択をできる社会構築のためには、都市ごとの課題に即した支援策が不可欠である。今後の少子高齢化・人口減少社会においては、女性配偶者の労働3加が地域経済の持続可能性を左右するカギとなるだろう。




コメント