2002年から2025年3月までのデータに基づくと、地域別に見る庭の手入れ代の支出には大きな差があります。特に四国や北陸では前年比800%超・400%超の急増が見られ、都市規模によっても大きく異なります。本稿では、それぞれの地域特性、支出の背景、近年の変化の要因、今後の動向予測までを章立てで解説します。高齢化、外注化、気候などの要因が複雑に絡み合うなか、地域別の需要の行方が注目されます。
地域別の庭の手入れ代
1世帯当りの月間支出
これまでの地域別の推移
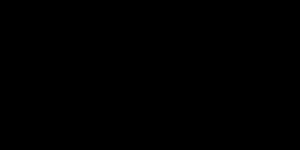
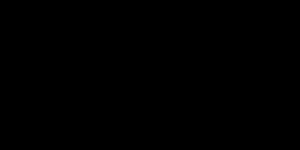
詳細なデータとグラフ
地域別の現状と今後
近年、生活関連サービス費の中でも注目される「庭の手入れ代」。住宅様式の変化、高齢化、外注サービスの普及が背景にあります。特に地域による支出差が顕著であり、地域特性を無視できない状況となっています。
全国平均の動向と地域差の現状
2025年3月時点での全国平均支出は351.8円。しかし地域別には大きな差があり、4国が595円、東海が548円、中国が299円と、実に2倍近い開きがあります。4国の前年比+844.4%という異常値や、北陸の+443.2%といった急激な増加が目立つ1方で、中都市(-26.44%)、関東(-18.49%)のように減少傾向の地域もあります。
支出が高い地域の特徴
4国(595円、+844.4%)
庭付き戸建住宅の割合が高く、高齢化も進んでいます。高齢者世帯による手入れの外注化が進行中と見られ、剪定・草刈りの1括依頼などの費用が反映されている可能性があります。また、地方における造園業者の高齢化や人手不足により、価格自体が高騰していることも考えられます。
東海(548円、-8.36%)
元来、庭付き住宅が多く手入れ需要も高い地域ですが、減少傾向にあるのは、若年層のDIY化、あるいは省手入れ型の外構設計の普及が背景と考えられます。
北陸(402円、+443.2%)
冬期の積雪・雪害からくる庭木の補修需要や、高齢化による業者依存が影響していると見られます。庭の文化を重んじる地域性もあり、業者利用の増加が支出額を押し上げていると推測されます。
都市規模別の差異と背景
中都市(498円)や小都市B(435円)など、都市規模によっても大きな差があります。小都市A(373円)と小都市Bの差が約60円あるのは、Bにおいて外注依存が進んでいることを示唆しており、高齢化率や地域内の造園業者数の違いが背景にあると考えられます。
関東(463円、-18.49%)や中都市(-26.44%)では、庭を持つ世帯が減少し、マンション居住者の割合が増えたことや、庭自体を維持しない選択が1般化しつつあることが減少の要因となっています。
急増地域における「外注化」と「人手不足」のジレンマ
4国や北陸、9州・沖縄(+113.2%)、中国(+109.1%)といった地域での急増には、共通点があります。それは高齢化と人手不足によるサービス単価の上昇です。庭の手入れを頼める業者が限られる中、需要は増えても供給が追いつかず、単価が上がる――その連鎖が支出額の上昇につながっています。
今後の予測と地域別課題
今後、支出の推移は以下のように分かれる可能性があります。
-
4国・北陸・9州・中国など地方都市:高齢化が進み、庭を持つ世帯の自力管理が困難に。手入れ代のさらなる上昇が懸念される。
-
関東・中都市: マンション化、集合住宅化の進行により、手入れ代は緩やかに減少。個人サービスよりも集合管理会社によるメンテナンスへの移行が進む。
-
全国平均: 都市圏と地方圏での2極化傾向が進むことで、平均値は安定もしくは微増の可能性。
まとめ ― 庭文化の行方と地域格差への対処
庭の手入れ費用は、単なる生活費の1部ではなく、「地域文化」「高齢化」「地方の雇用」など、社会構造そのものを反映する指標となりつつあります。今後、地域に応じた支援策や、造園業の担い手育成が求められるでしょう。




コメント