和服の世帯別支出は、就業者3人以上や6人以上の大家族で顕著な増加が見られ、特に就業者3人以上世帯は前年比1176%増と突出しています。これは成人式・卒業式など行事対応や伝統回帰の傾向が影響していると考えられます。一方で少人数・高齢世帯では支出が大きく減少しており、和服消費の二極化が進行中です。今後はイベント需要とともに、家庭内の就業構成が和装文化の担い手を左右する時代に入ると予測されます。
世帯別の和服
1世帯当りの月間使用料
これまでの世帯別の推移
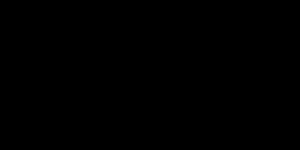
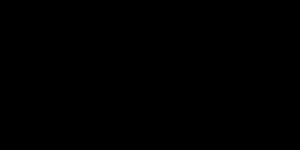
詳細なデータとグラフ
世帯別の現状と今後
和服は長らく日本の伝統衣装として、冠婚葬祭・節句・行事などの特別な場で用いられてきましたが、日常生活での着用機会は戦後の洋装化の進展で激減しました。2000年代以降の和服支出は、着物の価格高騰と利用場面の限定化により、継続的な減少傾向を辿っていました。しかし、2020年代に入ってからは若年層の着物回帰やリサイクル着物市場の活性化により、1部世帯での支出が再上昇傾向を見せています。
大家族・多就業者世帯に見られる支出急増の背景
今回のデータでは、「就業者3人以上世帯」が前年比1176%の支出増、「世帯6人以上」が315.6%増という非常に顕著な伸びを示しています。これは、多人数世帯の中に和服の利用機会を持つ若年層(成人式や卒業式対象者)が複数いる可能性、または行事を重んじる世帯文化が影響していると考えられます。複数人の節目行事が重なると、1気に支出が跳ね上がるためです。また、経済的に比較的安定している就業者数の多い世帯では、レンタルでなく購入という選択肢を選ぶ傾向も見られます。
支出減の世帯構成と課題
1方で「世帯2人」「就業者2人」「就業者0人」といった少人数・高齢化が進んだ世帯では支出が大きく減少しており、特に就業者2人世帯は前年比-70.47%、世帯2人は-69.02%と急激な減少を示しています。これらの世帯では、行事3加頻度が低く、和服の利用場面自体が少なくなっています。また、高齢者世帯では収納や維持の手間を嫌い、和服を敬遠する傾向も強まっています。
中間層(世帯3人〜5人)の分岐と背景要因
世帯3人〜5人に関しては、支出の上昇・下降が分かれる興味深い状況です。世帯4人・5人ではそれぞれ292.6%、2.765%とわずかに増加傾向がありますが、世帯3人では-60.1%と大幅減です。この差には「家族構成の年齢分布」が大きく影響していると考えられます。たとえば、子どもが小学生以下の世帯では和服需要は低く、逆に高校・大学進学を控えた子がいる世帯では着物が必要になるイベントが増えるためです。
リサイクル・レンタル市場の影響と新しい購買動向
2020年代以降、若年層を中心にリユース着物やレンタルサービスが普及し、「和服=高額」という固定観念が薄れつつあります。特に都市部やネット利用率の高い世帯では、ネットレンタルやメルカリなどのフリマアプリを活用して安価に和装を手に入れるケースが増えています。これが支出にどのように反映されるかは、家族内で「購入」か「レンタル」かの意思決定がどのようになされているかに依存しています。
今後の和服支出の展望と政策的視点
今後の和服支出は、「伝統行事の存続」「家族構成の多様化」「世帯内年齢分布」の3要素が重要な鍵になります。特に、教育機関と地域行事における和服着用の奨励、地方自治体による和装振興策(補助金やレンタル券の配布)などが行われれば、再び和服文化が見直され、支出増につながる可能性があります。加えて、観光地での着物体験を契機とした国内需要回帰も1部で期待されています。
まとめ ― 和服消費は「家族のかたち」に左右される
和服の世帯別支出は、単なる文化的嗜好ではなく、「世帯構造」と「経済的余裕」、そして「行事需要」によって大きく変動することが今回のデータから明らかです。消費が極端に2極化する今、和装文化の存続には、行事の意義や着用経験の継承が不可欠です。和服は贅沢品ではなく、日本の家族文化そのものを映す鏡となっていると言えるでしょう。




コメント