2025年4月の原動機付輸送機器の全国平均支出は25.8万円で、北陸や四国が突出。購入世帯は少ないものの、地域によっては高齢者の移動手段やEVモデルへの関心が高まっており、今後は電動スクーターや地方支援策を背景に支出の増加が期待される。
家計調査結果
原動機付輸送機器の相場
原動機付輸送機器支出の世帯割合
原動機付輸送機器の推移
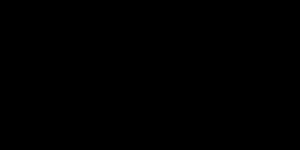
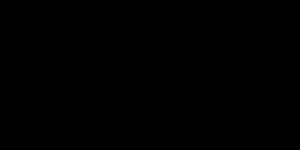
詳細なデータとグラフ
原動機付輸送機器の自動車関連現状と今後
原動機付輸送機器とは、主に排気量50〜125cc程度の小型バイク(原付)、スクーター、3輪バイク、電動バイクなどを指します。自転車よりも早く、軽自動車よりも維持費が安く、都市部や地方を問わず短距離移動において高い機動力を持つ交通手段として利用されてきました。
特に地方部では生活の足として不可欠であり、都市部でも宅配、通勤、買い物用途に広く活用されています。また近年では電動スクーターやシェアリングモビリティの普及により、新たな注目を集めているカテゴリでもあります。
全国と地域別の支出水準――北陸・4国の突出
2025年4月時点の全国平均支出は25.8万円。1世帯あたりとしては高額な買い物であり、家計の中でも耐久消費財に近い性質を持ちます。
特に支出が高いのは:
-
北陸:65.88万円
-
4国:50.84万円
-
小都市B:33.45万円
このような地域では、買い替えや1時的な需要の集中、あるいは複数台購入(家庭内や仕事用)による支出のブレが大きく表れている可能性があります。また、電動モデルや高性能モデルへの需要も1因と考えられます。
対照的に中都市(20.8万円)や近畿(21.1万円)は比較的抑えられており、これは既存車両の延命使用や購入時期の集中化が見られないことが関係していると推測できます。
前年同月比の増減から見える異変とトレンド
前年同月比の伸び率を見ると、4国(+234.5%)や9州・沖縄(+200.1%)のように極端な増加が見られます。これは以下のような複合的要因によると考えられます:
-
地方の高齢化と車からの代替手段の移行→ 車の運転が困難な高齢者層が、より簡便な移動手段として原動機付バイクに回帰している。
-
電動バイクなど新技術モデルへの買い替え需要→ 政府の補助金や、環境意識の高まりも拍車をかけている。
-
インフレや価格改定による単価上昇→ 製造コストの上昇により、1台あたりの価格が全体的に上昇傾向にある。
1方で、中都市は-28.5%と減少しており、過年度の大型需要の反動減や、購買意欲の鈍化が背景にあると見られます。
購入世帯割合の低さとその意味
原動機付輸送機器を実際に購入した世帯の割合は全国で0.263%と、非常に限られた層での支出であることがわかります。これは耐久財ゆえに頻繁に購入されるものではないという特性に加え、車社会の都市化、公共交通の発達、シェアリングサービスの代替化など、利用形態の変化も反映しています。
ただし、地域別で見ると9州・沖縄(0.28%)、中都市(0.27%)などで高く、これらの地域では依然として原動機付輸送機器が生活に欠かせない存在であることが示唆されます。
また、前年同月比での世帯割合の変動が非常に大きい(9州・沖縄は+600%など)点は、少数世帯の購入によって統計が大きく変動するほど利用層が限られていることの証左とも言えます。
抱える問題と今後のリスク
原動機付輸送機器市場は、以下のような課題を抱えています:
-
若年層のバイク離れ→ 維持費、駐車場の確保、安全性への懸念などから、20代以下の所有率は年々減少。
-
安全性・事故リスク→ 車体が小さく、事故時の被害が大きいため、高齢者や初心者にとっては敷居が高い。
-
販売体制の縮小→ 地方での販売店・整備網の縮小により、購入やメンテナンスが困難な地域も増えている。
-
EVシフトの中での中途半端な位置づけ→ ガソリン車でも電動車でもない“中間領域”の商品が多く、消費者にとって選択肢が不明瞭。
今後の期待と展望
今後の原動機付輸送機器支出は、以下のトレンドにより1定の回復と再注目が期待されます:
-
高齢者向け電動スクーターの普及→ 安全支援機能付きの電動モデルの開発により、移動支援ツールとしての普及が進む可能性。
-
インフラ整備とシェア型導入の拡大→ 都市部ではガソリン式よりも電動シェアバイクに需要が移行し、支出形態が“個人購入”から“利用料支出”へと変わっていくと予測される。
-
地方自治体による移動支援政策→ 地方部では自治体が移動手段として原動機付バイクの導入を後押しする動きが強まるかもしれない。
-
気候変動への対応需要→ CO₂排出の少ない移動手段として、ガソリン車からの乗り換え需要が発生する可能性もある。



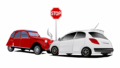
コメント