勤労世帯の預貯金は地域差が大きく、仙台市が115.3万円と突出している一方、宮崎市や神戸市では30万円前後にとどまっています。年齢や世帯構造、地域経済の状況が影響しており、若年層や低所得地域では貯蓄が難しい傾向です。今後は、インフレや将来不安に備えた預貯金の重要性が増す一方、資産形成支援や地域間格差の是正が課題です。
預貯金の家計調査結果
預貯金の多い都市
預貯金の少ない都市
これまでの預貯金の推移
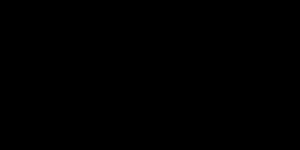
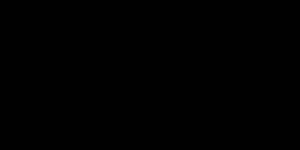
詳細なデータとグラフ
預貯金の現状と今後
預貯金は、日本の家計にとって生活の安定を支える中心的な資産です。物価上昇や景気の不安定さが続く中、現金・預金という安全資産への信頼は根強く、勤労世帯においてもその傾向は強まっています。今回のデータからも、都市ごとの預貯金額に大きなばらつきが見られ、地域経済や生活コスト、世帯構造の違いが影響していることが分かります。
預貯金の全国動向と長期的推移
2025年3月時点での全国平均の預貯金額は42.74万円と、堅調に推移しています。2000年以降を振り返ると、リーマンショックや東日本大震災後の景気低迷を経て、金融緩和政策による低金利環境が続いたこともあり、現金・預金重視の傾向は強まりました。近年はインフレ傾向にあるものの、リスク資産への投資よりも預貯金を選好する世帯が多数派です。
都市別の預貯金水準 ― 仙台市が突出した理由
仙台市が115.3万円と、全国平均の約2.7倍という突出した数値を示しています。前年同期比で+178.9%という大幅な増加があり、これは1時的な高額賞与や臨時収入、公務員比率の高い地域特性などが影響していると考えられます。また、仙台市は東北地方の中核都市として、所得水準が比較的高いことも影響しています。
1方、預貯金が少ない都市としては、宮崎市や神戸市、甲府市などが挙げられます。これらの都市では、労働市場の脆弱性や生活コストとのバランスが悪いこと、雇用の安定性に欠ける点などが影響している可能性があります。
増加と減少の要因分析 ― 地域経済と家計戦略の違い
預貯金の増加率においても、地域間で大きな差があります。山口市(+70.67%)、広島市(+47.32%)、北9州市(+36.61%)などは、公共工事や地元産業の回復などで収入が増加し、貯蓄余力が高まった可能性があります。
1方、堺市(-27.46%)、青森市(-21.28%)など大幅な減少が見られる地域では、医療・福祉費の増加や生活費の上昇が貯蓄を圧迫していると推測されます。
世代間の預貯金傾向 ― 若年世帯と中高年世帯の違い
勤労世帯における預貯金額は、年齢とともに上昇する傾向があります。若年層は可処分所得が低く、住宅ローンや教育費の支出が重く、貯蓄に回す余力が少ない1方、中高年層では収入の安定や子育ての終了によって貯蓄可能額が増加します。
また、近年の若年層では、低金利・将来不安から投資よりも預貯金を優先する「守りの家計」が見られますが、その1方で、インフレへの対応力には課題が残ります。
今後の展望と課題 ― 資産形成と地域格差の是正
今後もインフレや社会保障制度の見直しが進む中で、預貯金の役割はさらに重要になります。1方で、都市間格差や世代間格差が拡大するおそれがあり、家計における資産形成の支援が求められます。NISAやiDeCoといった制度を通じた分散投資の促進や、地域ごとの金融教育の充実が課題となります。
また、自治体や企業による家計支援策も、預貯金格差是正に貢献しうる重要な要素となるでしょう。




コメント