勤労世帯の財産収入は全国平均0.166万円と極めて低く、都市間・世代間で大きな差があります。徳島市や宇都宮市などは資産運用や不動産収入で上位を占める一方、多くの都市ではゼロに近い水準です。若年層は投資余力が乏しく、格差拡大の懸念もあります。今後は金融教育と制度活用が重要です。
財産収入の家計調査結果
財産収入の多い都市
財産収入の少ない都市
これまでの財産収入の推移
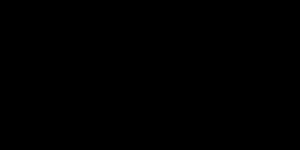
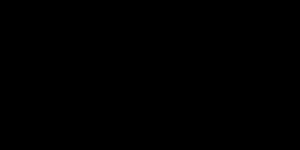
詳細なデータとグラフ
財産収入の現状と今後
財産収入とは、預貯金利子、株式配当、不動産賃貸収入、投資信託分配金など、勤労収入とは別に得られる「資産からの所得」です。これは勤労世帯の経済的安定性や資産形成の成熟度を表す指標であり、高齢期の生活や将来の家計設計にも直結する重要な収入源です。しかし日本においては、勤労世帯の財産収入は非常に小さい割合にとどまっており、全国平均は2025年3月時点で0.166万円(1,660円)と極めて低水準です。
これまでの動向 ― 20年間の推移と背景
2000年以降の長期的な動向を振り返ると、日本の財産収入は伸び悩んできました。これは以下のような構造的要因が影響しています:
-
超低金利時代の長期化により、預貯金の利子がほとんどつかず、銀行口座からの収入は無に等しい
-
日本人の投資意識の弱さ:株式や不動産への投資が欧米と比べて消極的で、資産を「増やす」文化が根づきにくい
-
若年世帯の可処分所得の低さ:そもそも投資に回す余力が少なく、財産収入に結びつかない
その結果、多くの勤労世帯は財産収入に依存せず、主に労働によって生計を立ててきた実態があります。
都市間格差の顕著化 ― 財産収入の高い都市・低い都市
今回の家計調査では、徳島市(0.485万円)や宇都宮市(0.431万円)、岐阜市(0.412万円)などが財産収入の多い都市として浮上しました。これらの都市には以下のような傾向が見られます:
-
中小企業経営者や自営業者が多く、不動産や金融資産を持つ傾向がある
-
地価が比較的安定しており、賃貸不動産の収益が家計に組み込まれている
-
高齢者比率が高く、年金以外に資産運用を行っている層が1定数存在する
1方、仙台市・札幌市・福岡市など大都市を含む複数都市では、財産収入が前年同期比で100%減(実質ゼロ)となっており、都市の規模と財産収入の多寡は必ずしも1致しません。大都市では生活費が高く、若年層の割合も高いため、投資に回す余力が乏しい世帯が多いと考えられます。
世代間の違い ― 投資経験とリスク許容度のギャップ
財産収入において世代間の格差も顕著です。中高年層や退職前後の世帯は、長年の貯蓄や投資経験を活かし、株式配当や不動産収入を得ている場合がある1方で、若年世帯は依然として労働所得に依存しています。
さらに、若い世代ではリスク資産への不安や金融知識の不足により、NISAやiDeCoを活用しきれていない実情があります。この世代間の投資・収入格差が、今後の経済的格差につながる可能性も懸念されます。
今後の展望 ― 財産収入は増えるのか?
日本政府は資産所得倍増計画などを通じて、家計の投資促進を後押ししています。特に2024年以降の新NISA制度の開始により、非課税投資枠の拡大や長期投資の後押しが進められています。
しかし、現実的には以下の課題が残ります:
-
資産形成に回す可処分所得がない世帯の多さ
-
金融教育の不足により、制度の利用が偏在している
-
地域によって金融商品の普及度や不動産投資環境が異なる
これらを解決するためには、学校教育や地域単位での金融リテラシー教育の推進、公的支援制度のさらなる普及が不可欠です。
政策提言と家計のあり方 ― 収入の多元化を目指して
日本の家計が今後持続可能な資産形成を目指すには、「働くこと」だけでなく、「資産を活用する」視点が必要です。家計調査が示すように、財産収入は現時点ではわずかですが、これを育てることで将来の生活安定につながります。
政策面では、所得再分配と同時に、資産形成の初期支援(例えば、若年層向けNISA給付)など、階層間格差を埋める支援が鍵となるでしょう。
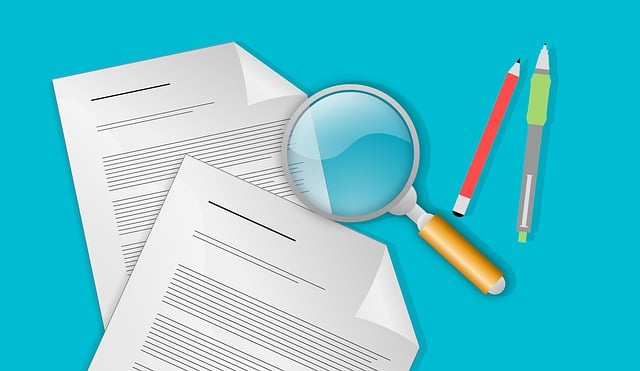



コメント