勤労世帯の定期収入は、都市ごとに大きな格差が見られ、さいたま市や千葉市など関東圏で高水準を維持する一方、那覇市や神戸市などでは低迷が続く。背景には雇用構造、産業集積、物価水準、世代構成などがあり、近年は地方圏の落ち込みが顕著。今後は高齢化や非正規雇用の増加が収入に影響を及ぼすと予想され、地域別の政策的対応が求められる。
定期収入の家計調査結果
定期収入の多い都市
定期収入の少ない都市
これまでの定期収入の推移
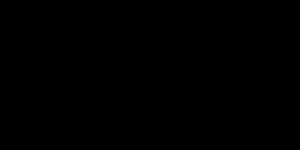
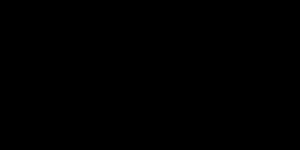
詳細なデータとグラフ
定期収入の現状と今後
定期収入とは、勤労世帯における主な収入源である「毎月の給与」や「ボーナス」など、継続性のある収入を指します。経常収入にはこの定期収入に加えて、臨時収入や副業・事業収入、社会保障給付などが含まれますが、定期収入は生活の基礎をなす重要な指標であり、家計の安定性を測るバロメーターでもあります。
全体的な推移と長期的な課題
全国平均の定期収入は最新で50.1万円。これは2000年代初頭と比較して大きな伸びはなく、物価上昇や社会保険料の負担増加を考慮すると、実質的な可処分所得はむしろ目減りしている可能性が高いです。特に2010年代以降、非正規雇用の増加や、企業の賃金抑制傾向が影響を与えており、所得の伸びが停滞する中で、支出だけが増える「実質賃金マイナス」の局面が続いています。
定期収入の高い都市の特徴と背景
さいたま市(64.86万円)・千葉市(63.84万円)・広島市(63.73万円)
これらの都市は大都市圏の周辺に位置し、首都圏に準ずる経済活動が行われているため、高収入の企業勤務者や共働き世帯が多く存在します。特に広島市は前年比+51.8%という異常値に近い伸びを示しており、1時的な要因(例えば賞与増加や大企業の臨時支給など)が含まれている可能性もあります。
東京都区部(61.93万円)・川崎市(60.73万円)
本来高水準であるべき東京都区部と川崎市ですが、前年比でマイナス(東京都区部は-7.949%、川崎市は-7.558%)と減少が見られます。これは企業業績の1時的な不振や、在宅勤務の増加により残業代等が減少した影響、あるいは調査対象層の変化などが影響していると推察されます。
定期収入の低い都市に見る構造的課題
那覇市(33.94万円)・神戸市(35.34万円)
那覇市は観光業依存が高く、コロナ禍後の回復が進んでいるとはいえ、サービス業中心で平均賃金が低くなりがちです。神戸市は都市規模に比して定期収入が非常に低く、前年比も-16.55%と大幅に減少しており、製造業の衰退や高齢化、非正規雇用比率の高さが課題です。
堺市・甲府市・青森市などの地方都市
堺市の前年比-24.35%、青森市-15.85%などの大幅減は、地方圏の構造的な雇用問題(雇用のミスマッチ・若年層の流出)や、地域経済の縮小が背景にあります。これらの地域では、公的部門以外の安定的な高収入職の不足が、定期収入の水準を押し下げています。
世代間の収入差と家計構造の変化
若年層の定期収入は全体的に伸び悩んでおり、非正規比率の高止まりや企業内賃金格差の固定化により、若年層が家計を支える力が弱まっています。1方、中高年層では年功序列型の給与体系が今も1部で維持されているため、都市部では世帯主が40代・50代である家庭が高収入の傾向を示します。
また、共働き世帯が増える1方で、扶養の範囲内で働く配偶者が多く、全体の世帯収入に十分反映されていないケースもあります。
今後の定期収入の展望と政策的課題
都市間格差の拡大の可能性
広島市や山形市、山口市など、地方でも1定の伸びが見られる都市がある1方で、神戸市や堺市のように大幅に落ち込む都市もあり、2極化が進行しています。この傾向は今後さらに強まる可能性があり、地域産業の再生や若年層の定着策が急務です。
非正規化・柔軟雇用の増加が与える影響
定期収入の主たる構成は正規雇用の給与です。今後、非正規雇用が労働市場の多数を占めるようになると、安定的な定期収入の水準がさらに下がり、都市部でも所得の不安定化が進む可能性があります。
政策の方向性
地域ごとの最低賃金の底上げや、子育て・教育支援を通じた世帯支出の抑制も、実質的な家計支援策となり得ます。また、企業への賃上げ要請や、テレワーク時代に合った新たな雇用形態の整備も課題です。
おわりに
定期収入は家計の安定に直結する重要な経済指標であり、都市間・世代間での差異は、今後の地域政策や社会保障制度設計にも大きな影響を及ぼします。経済の構造変化に応じた柔軟な政策対応と、地域の特性を踏まえた雇用創出こそが、持続的な所得向上の鍵となるでしょう。




コメント