日本の出前購入額は2025年4月で平均9,847円。近畿や九州で特に支出が高く、前年同月比で全体的に増加傾向にある。一方、出前を利用した世帯の割合は減少し、定期利用層への集中が進んでいる。今後は利便性と健康志向を両立したサービスが鍵。
家計調査結果
出前の相場
出前支出の世帯割合
出前の推移
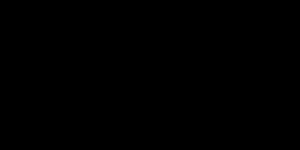
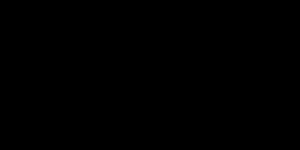
詳細なデータとグラフ
出前の食料品現状と今後
2025年4月時点で、日本の世帯における出前の月間平均支出は9,847円となっており、前年同月比で+4.708%の増加が見られます。これは、食の多様化や利便性の重視、共働き世帯の増加などの背景が影響していると考えられます。
また、新型コロナウイルスの影響で高まった“中食”(なかしょく)文化の定着が、出前需要の底上げを継続的にもたらしているといえます。
地域別支出の特色と傾向
出前支出額トップ:近畿・9州・中都市
最も支出が高いのは近畿(12,000円)で、次いで9州・沖縄(11,210円)、中都市(10,490円)が続きます。これらの地域では、人口集中度や都市機能の発達、飲食店の宅配対応力が出前支出に影響していると考えられます。
特に近畿の+22.26%という急増は、物価上昇の中でも利便性を優先する家庭が出前を選ぶ傾向を強めたことの表れです。
出前支出額の増加が限定的な地域
1方で、小都市A(+1.181%)や関東(+2.892%)は増加幅が小さく、既に出前文化が定着して飽和状態にある可能性があります。
出前利用世帯の割合と変化
出前を利用した世帯の割合は全国平均で5.52%。最も高いのは近畿(5.77%)と全国平均(6.39%)ですが、前年同月比では-15.02%と減少しており、利用者数が減っている中で、利用世帯1軒あたりの支出が増えていることがうかがえます。
これは、出前利用の「2極化」が進んでいる可能性を示唆しています。すなわち、「定期的に出前を頼む層」と「全く頼まない層」の分化です。
出前利用の課題と懸念
コストの上昇と継続性の問題
出前価格には、料理代に加えて配送料・手数料が上乗せされるため、家計を圧迫しやすく、今後も価格の上昇が続けば利用頻度の減少に繋がる懸念があります。
② 地域格差の拡大
東北(3.07%)や中国(3.77%)など出前文化の浸透が遅れている地域では、サービスの選択肢が少なく、配達エリアの限定が利用の障壁となっています。
③ 健康面への影響
出前食品は高カロリー・高脂質になりがちであり、健康志向の高まりとのギャップが拡大すると、今後の支出に影響する可能性があります。
今後の出前市場の推移と期待
利用世帯の減少、支出額の高止まりへ
利用世帯の割合は前年比で減少傾向にある1方、支出額は引き続き高い水準を維持しています。今後もこの傾向は続き、「1部の固定利用者による高額支出」が市場を支える形になると予想されます。
技術革新と宅配網の改善に期待
AIによる配送効率化や無人配達・ドローン導入などのテクノロジー進化によって、配送料削減やサービス範囲拡大が期待されます。特に中山間地域へのサービス普及が鍵となります。
サブスク型やヘルシー志向の拡大
健康意識に応える低糖質・高タンパクの出前商品や定額制の出前サービスが広がれば、出前支出は今後も安定的に拡大する可能性を秘めています。




コメント