住宅形態による仕送り金支出には大きな格差が見られます。給与住宅や住宅ローンを抱える持ち家では仕送り額が高く、経済的余力や家計運営のスタンスが影響しています。一方、公営住宅やURなどでは支出が著しく低く、収入制限や生活保護に近い世帯構成が背景にあります。近年のデータでは大半の住宅形態で支出が減少し、家計の引き締めが進んでいる一方、公営住宅では異例の増加も見られ、今後の格差拡大を示唆しています。
住宅別の仕送り金
1世帯当りの月間支出
これまでの住宅別の推移
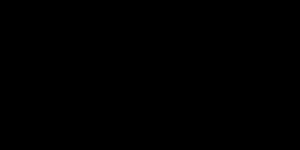
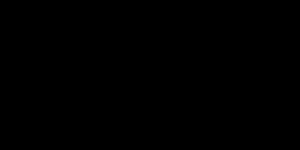
詳細なデータとグラフ
住宅別の現状と今後
住宅の種類は世帯の経済力を象徴する1因であり、仕送り金の支出額にも明確な違いをもたらしています。給与住宅や住宅ローン付きの持ち家などは高所得層が中心となり、生活に1定の余裕があるため仕送りにも積極的です。1方、公営住宅や都市再生機構(UR)住宅などは、家賃が安価な分、生活保護に近い経済状況の世帯が多く、仕送りは控えめになります。
最新データに見る住宅別支出の格差
2025年3月時点のデータでは、給与住宅が3696円、ローン付き持ち家が3273円、1般の持ち家が2490円と高額な仕送りが行われているのに対し、民営住宅1987円、公営住宅1271円、UR住宅に至ってはわずか256円と極端な格差が存在しています。この差は、可処分所得の違いだけでなく、子世帯への支援意欲や文化的背景、さらには住宅政策の影響も絡んでいます。
前年同期比から見える変化と課題
前年同期比では、持ち家で-20.37%、民営住宅で-28.14%、UR住宅で-88.17%と、ほぼすべての住宅形態で支出が大幅に減少しています。これは、電気代や食品など生活必需品の物価高騰によって、仕送りという「削れる支出」が抑制されていることを反映しています。1方で、公営住宅は+388.8%という異常な増加を記録しており、生活保護受給者の1部が仕送りを再開した、あるいは親族支援が急務になったケースが想定されます。
住宅別特徴と家計戦略の違い
-
給与住宅:企業からの福利厚生による居住のため、家賃負担が軽く、仕送りに回せる余裕がある。高収入世帯が多い。
-
住宅ローンありの持ち家:ローン負担が大きい1方で、安定収入のある世帯が多く、子どもへの支援意識も強い。
-
民営住宅:賃貸料が高いため、仕送り支出が下がる傾向。共働き世帯も多く、教育費優先になることも。
-
公営住宅・UR住宅:低所得者層中心。特にURは中高齢単身者が多く、仕送りを受ける側に回るケースが多い。
今後の推移と政策的課題
住宅に起因する経済格差は、仕送り支出の面でも今後さらに拡大する可能性があります。少子高齢化と都市集中によって、親が郊外で、子が都市部に暮らすパターンが増加する中、住宅費の差が仕送り能力を左右する局面は続くでしょう。また、公的住宅に住む層の高齢化が進めば、今後は「仕送りする側」から「受ける側」への転換が進みます。これは家族間扶助制度だけでなく、公的支援制度の再設計にもつながる重要な指標です。
社会と文化の変化が与える影響
仕送りという行為そのものが、親と子の経済的つながりを象徴する日本特有の文化でもあります。しかし、若年層の非正規化・低収入化、親世代の生活防衛志向の強まりにより、この文化は今後縮小する可能性があります。住宅事情の変化(たとえば定年後の住み替えや、高齢者住宅への移行)も、この仕送り関係のあり方に少なからず影響を与えていくでしょう。
以上のように、住宅の形態は単なる居住環境以上に、家計構造や仕送り金の支出に深く結びついています。物価上昇が続く中で、仕送りという家族支援文化は見直しの時期を迎えており、住宅環境による格差も重要な視点として今後注目されるべきです。




コメント