住宅形態別のタンス支出では、住宅ローンを抱える持ち家世帯が最も高く、収納需要が生活の変化に直結していることが分かります。一方で、公営住宅や民間賃貸では、収納不足を補う需要が見られつつも、住環境の変化により支出のばらつきも目立ちます。今後は住宅の設備差やライフスタイルの変化に応じた収納家具が求められると予測されます。
住宅別のタンス
1世帯当りの月間支出
これまでの住宅別の推移
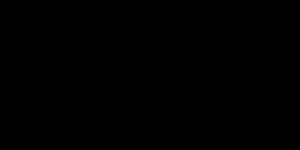
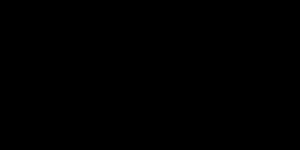
詳細なデータとグラフ
住宅別の現状と今後
タンスは家庭内収納の代表的家具として長年使われてきましたが、住宅の構造や生活スタイルの変化により、その需要は大きく変動してきました。住宅の種類ごとにタンスの支出には明確な傾向が見られます。本章では、2002年から2025年3月までの長期データに基づき、住宅別のタンス支出の特徴や背景、将来の見通しを丁寧に解説します。
住宅別のタンス支出状況とその背景
最新データでは、「持ち家(住宅ローン有り)」が211円で最も高く、以下「持ち家(ローン無し)」108円、「民営住宅」106円、「その他」101円、「公営住宅」77円と続きます。
-
住宅ローン有りの持ち家世帯は、子育て世帯や若年層が多いとされ、新生活の準備や成長に伴う収納増加からタンス購入が活発です。支出が高いのは自然な傾向です。
-
持ち家(ローン完済含む)世帯では設備がすでに整っており、家具の新規購入は少なく、買い替えや補充的需要にとどまると考えられます。
-
民営賃貸住宅では、家具付き物件や収納が限られていることから、タンスの補完的需要があります。+23.26%という増加は、賃貸住まいでも収納を重視する傾向の現れかもしれません。
-
その他住宅(社宅・官舎など)は1気に-62.31%と大幅減。住環境が1時的・簡素な場合が多く、家具購入を避ける傾向が強くなった可能性があります。
-
公営住宅では77円と少額ながら、+75%と大幅増。収入が限られる層の中で、必要最低限の収納ニーズが再燃していると考えられます。
支出増減の背景にある住宅事情
住宅の種類によってタンス支出に違いが生じる理由は、以下のような住宅環境の差異に起因します。
-
収納環境の差:新築や分譲住宅には多くの収納スペースが備わっており、家具の必要性が少ない。1方、古い公営・民営住宅では収納が不足し、タンスが必要になる場合がある。
-
家族構成と住宅の相関:住宅ローンを抱える世帯は家族が多く、収納量も多くなる。これがタンス支出の高さに結びついています。
-
住居の流動性:賃貸や1時的住居では、引っ越しを前提とした生活が多く、大型家具の購入が控えられる傾向があります。
今後のタンス需要の展望
住宅事情とライフスタイルの変化に伴い、今後のタンス需要は以下のように推移すると見られます。
-
持ち家(ローン有り)での需要は高水準維持:住宅ローン返済中の世帯は比較的若年で、今後も生活の充実を図る過程で収納家具の需要が安定的に続くと考えられます。
-
公営・民営住宅では波がある:1部では増加傾向にありますが、生活支援政策や住環境の整備が進む中で、家具の支出にばらつきが見られる可能性があります。
-
タンス自体の役割の変化:近年ではウォークインクローゼットの普及や衣類収納の簡素化が進み、タンスは以前より重要度を下げています。代替品(収納ケース、システム収納)の台頭もタンス需要の減少に影響しています。
政策・企業への示唆
住宅政策においては、収納不足が家具購入に直結しているケースも多く、特に低所得世帯への住宅改善施策が家具支出に間接的影響を与える点は注目に値します。企業にとっては、「狭小住宅向け」「分解・移動可能」な収納家具の提案が今後の需要獲得における鍵となるでしょう。



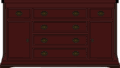
コメント