2025年3月までの家計調査によると、二人以上世帯の消費支出(住居費除く)は都市間で大きな差が見られます。名古屋市など都市部で支出が高い一方、那覇市や和歌山市などでは支出が低迷。世代構成や物価、雇用環境が背景にあり、今後は高齢化や地域経済格差が消費動向に影響を与えると予測されます。
消費支出(除く住居等)の家計調査結果
消費支出(除く住居等)の多い都市
消費支出(除く住居等)の少ない都市
これまでの消費支出(除く住居等)の推移
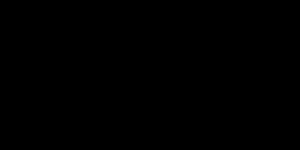
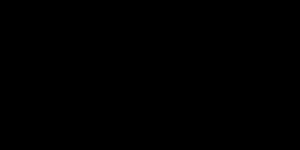
詳細なデータとグラフ
消費支出(除く住居等)の現状と今後
日本の家計における消費支出は、長期的に見て緩やかな減少傾向を続けてきました。とくに2010年代は、デフレや経済の停滞、消費増税の影響で消費意欲が抑えられた時期が続きました。
住居費を除いた消費支出(例えば、食費、交通・通信、教育、娯楽など)は、生活の質や経済活動の活発さを反映する指標です。2025年3月時点での全国平均は29.31万円となっており、2020年のコロナ禍以降、緩やかな回復を見せています。ただし、物価上昇がこの数字の押し上げ要因でもあるため、実質的な消費意欲が高まっているかには慎重な分析が必要です。
都市間の支出格差の特徴
消費支出額を都市別に見ると、名古屋市(38.02万円)や広島市(36.87万円)が高く、那覇市(22.1万円)や和歌山市(22.79万円)は低いという顕著な差が出ています。
高支出都市の特徴
-
名古屋市・広島市・東京都区部など: 大都市圏では所得水準が比較的高く、交通や教育、娯楽など多様なサービスへのアクセスが豊富なため、自然と支出水準が上がります。
-
山形市・富山市など地方中核都市: 1見意外に見えるが、生活水準が安定しており、医療や教育、車社会ゆえの交通費などが支出を押し上げている可能性があります。
低支出都市の特徴
-
那覇市・和歌山市・津市など: 地方都市では可処分所得が低めであることに加え、物価や生活コストが低い地域も多く、支出そのものが抑制されがちです。また、世帯構成として高齢者の割合が高いことも影響しています。
世代間の違いと消費傾向
消費支出の中身を見ると、世代によって優先される費目が異なります。
-
高齢世帯(60代以上):医療費や食品に比重。安定志向が強く、支出は抑え気味。
-
子育て世代(30~40代): 教育費、被服、外食などが多く、支出総額も高くなる傾向。
-
若年単身世帯(20代): 支出額は抑えめだが、通信費や娯楽に集中することも。
今回の調査は「2人以上世帯」対象であり、子育てや夫婦のレジャー、老後生活費が支出に大きく影響します。都市部では核家族化が進んでいるため、世代構成による支出の偏りも出やすくなっています。
増加率から見る地域経済の動き
前年同期比で見た場合、名古屋市(+28.5%)、広島市(+33.25%)などは大きく伸びています。これは地元経済の回復や物価上昇により消費額が増えたと考えられます。
1方で、津市(-10.53%)、神戸市(-9.961%)、金沢市(-13.43%)などはマイナス成長を記録。地元産業の衰退や人口減少など、構造的な課題が影響している可能性があります。
今後の予測と課題
予測①:インフレによる名目支出の増加
今後も1定のインフレが続く場合、名目上の消費支出は増えるでしょう。しかし実質的な購買力の向上が伴わなければ、生活満足度は上がらないままになります。
予測②:高齢化と消費構造の変化
高齢化の進行により、医療や介護関連支出が増加し、娯楽や教育などの消費が相対的に減ると予想されます。また、移動や外出が減ることで、交通費や外食費なども低下する傾向があります。
予測③:地方都市の厳しさと格差拡大
地方では人口減少・若年層流出が進んでおり、消費支出の伸び悩みが続く可能性があります。反対に、インフラや雇用の集中する都市圏では支出水準の維持または上昇が見込まれ、格差の拡大が懸念されます。
政策的対応と家計管理の重要性
今後の消費支出を健全に保つためには、政府による以下のような支援が重要です:
-
地方経済の再生による地域内消費の活性化
-
子育て世代への教育・住宅費支援
-
高齢者の生活支援と医療費負担の軽減
1方、家計側も物価の変動に対応するための柔軟な予算配分や、固定費の見直しが必要になります。住居費を除く支出は比較的コントロールしやすいため、節約や効率的な消費の工夫が家計防衛の鍵となります。
まとめ
2人以上世帯の消費支出(除く住居等)は、都市ごとの物価・所得・世代構成の違いを反映しており、地域間の格差が明確に現れています。今後も高齢化・人口動態の変化・インフレによる支出構造の変化が予想される中、政策対応と家計の自衛的工夫がより重要となってくるでしょう。




コメント