2008年から2025年までの家計調査データをもとに、二人以上世帯の洋服支出の推移を都市別・世代別に分析。川崎市や富山市など一部都市で急増が見られる一方、佐賀市や那覇市などでは大幅減少が目立つ。こうした変化には物価上昇、ライフスタイルの変化、購買チャネルの多様化、地域の産業構造や気候条件などが影響しており、今後の洋服支出も所得格差やEC化の進展により地域差がさらに広がる可能性がある。
洋服の家計調査結果
洋服の多い都市
洋服の少ない都市
これまでの洋服の推移
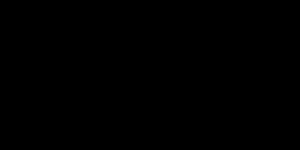
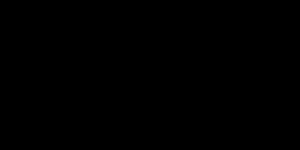
詳細なデータとグラフ
洋服の洋服現状と今後
2025年3月時点での洋服の平均支出は4796円となっており、これは2008年以降の長期的な傾向を踏まえると、中間的あるいはやや下振れした水準といえる。リーマン・ショック直後やコロナ禍では衣料品全体の支出が落ち込み、特に外出機会の減少が大きく影響した。しかし2022年以降は再び緩やかな回復傾向が見られている。
都市間の支出差—川崎市と佐賀市の極端な対比
支出が多い都市
-
川崎市(11620円、前年比+147.1%)
-
東京都心への通勤層が多く、ファッション消費意識も高い
-
高所得世帯や共働き世帯比率が高く、支出余力がある
-
リモートワーク緩和後の衣類需要の再燃も影響
-
-
富山市(8575円、前年比+97.99%)
-
地場百貨店・セレクトショップの充実や寒冷地での衣類需要
-
1時的な催事やセールによる消費拡大の可能性
-
支出が少ない都市
-
佐賀市(1559円、前年比-66.47%)
-
地方都市特有の物価抑制傾向、消費抑制志向
-
EC利用比率の高さにより店舗での支出が反映されにくい
-
-
那覇市(2056円、前年比-29.15%)
-
年間を通じて温暖な気候のため、衣類購入の頻度が少ない
-
カジュアル需要が中心で、高価格帯衣類の購入が限定的
-
支出傾向にみる世代間の特徴
洋服支出の傾向は、都市の年齢構成や家族構成にも左右される。以下が特徴的なポイントである。
-
若年層が多い都市(例:川崎市)
-
ファッショントレンドへの感度が高く、購買意欲も強い
-
ECサイトやブランド店舗へのアクセス性が良好
-
-
高齢化が進む都市(例:佐賀市、福島市)
-
消費全体が抑制され、衣料品の新規購入頻度が低下
-
機能性や実用性を重視し、支出額が限定されがち
-
オンライン購買とリアル店舗の2極化
都市によっては、EC化の進展が洋服支出の地域差に表れている。オンライン中心で購入する地域ほど、家計調査に反映される「支出」は少なくなりがちである。
-
都市部:店舗購入とECを併用、支出が家計調査に反映されやすい
-
地方:EC偏重、特にユニクロ・Amazon・楽天などが主流
-
地方では宅配インフラの進展と相まって店舗離れが進む
-
今後の洋服支出の展望と課題
短期的な予測(〜2026年)
-
2024年度以降の賃上げの定着次第では、都市部中心に支出増加の可能性
-
春夏物需要やインバウンド再活性による1部地域の衣料販売活況
中長期的な見通し(〜2030年)
-
気候変動とカジュアル化が進み、衣類の「買い替え」頻度が減少傾向に
-
サステナブル消費(中古市場、リサイクル品など)への移行が進む
-
高齢化の進展により「おしゃれより快適」を志向する支出が増加
政策的・社会的示唆
-
消費喚起策としての地域クーポンやファッションイベントの活用が求められる
-
地域の百貨店や衣料店の役割見直しと、若年層向け商品展開が鍵
-
生活コスト全体の上昇を踏まえた、コスパ重視型商品ラインナップの整備
このように、2人以上世帯における洋服支出は、単なる嗜好の違い以上に、地域の気候、世代構成、所得水準、購買チャネルの変化などが複雑に絡み合って決まっている。今後もこの傾向は続き、地域ごとの支出格差がより顕著になることが予想される。




コメント