家計調査によると、2025年3月時点の二人以上世帯の月間食料費は平均9.041万円。さいたま市や東京都区部など都市部で高額化が進み、広島市や富山市では前年比2桁の伸び。一方、青森市や岐阜市など地方都市ではマイナス傾向も。本稿では都市間や世代間の特徴、これまでの推移、今後の見通しについて分析する。
月間食料費の家計調査結果
月間食料費の多い都市
月間食料費の少ない都市
これまでの月間食料費の推移
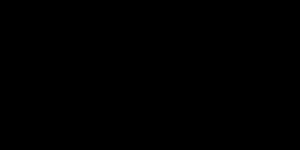
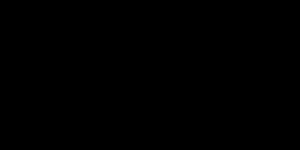
詳細なデータとグラフ
月間食料費の食料費現状と今後
2008年以降、2人以上世帯の月間食料費は緩やかに増加傾向にありましたが、特に2020年以降の物価上昇局面により明確な上昇に転じました。背景には原材料価格の高騰、円安、物流コストの上昇などがあります。2025年3月時点では平均9.041万円と、2008年初頭に比べて実質で1割近く増加しています。また、2020〜2022年のコロナ禍においては1時的に食料支出が増減する月もありましたが、全体としては「自炊需要の増加」により食料費が底堅く推移してきました。
都市間での食料費の格差
都市別の食料費では、さいたま市(10.93万円)や東京都区部(10.83万円)などの首都圏都市が軒並み高水準を記録。1方、那覇市(7.915万円)や和歌山市(7.981万円)などの地方中小都市では低水準です。この差は単なる物価水準ではなく、以下のような複合要因によります:
-
都市部:共働き世帯が多く、外食や中食利用が高いため食費がかさむ
-
地方部:自家消費(家庭菜園や親族の農産物の提供)比率が高く、購入支出が少ない
-
物価の地域差に加え、流通経路や生活スタイルの違いも反映されている
興味深いのは、広島市(前年比+21.18%)や富山市(+16.56%)のように、地方都市でも急増している地域がある点で、これはスーパーマーケットの高価格化や地元特産品の値上げの影響があるとみられます。
世代間の特徴と家族構成の影響
世帯の食費は家族構成と年齢層によっても大きく左右されます。特に以下の点が特徴です:
-
子育て世帯:食料費が高く、加工食品・冷凍食品・外食の割合が高い
-
高齢世帯:食費は抑制傾向だが、健康志向で高品質食品への支出が目立つ
-
若年夫婦世帯:外食比率が高く、都市部では食費が高くなりやすい
都市によって世帯構成の傾向も異なるため、たとえばファミリー層が多いさいたま市などでは高水準になりがちです。
物価上昇と可処分所得の関係
名目上の食費増加が続いていても、実質的には「可処分所得のうちに占める食費の割合(エンゲル係数)」は世帯の生活の厳しさを示す指標となります。今回のデータでは月間食費は増加していますが、所得が追いついていない世帯では食料費の上昇が他の支出を圧迫していることが想定されます。
地方では賃金が上がりにくい現状があるため、月間食費の増加が実質的な生活困窮と直結する傾向が強くなってきています。
今後の予測と政策的視点
今後数年にわたっても、以下の理由から月間食料費はじわじわ上昇する可能性が高いと考えられます:
-
食品メーカーの再値上げ(コスト高転嫁)
-
輸入食品依存のリスク(円安、地政学的要因)
-
高齢化社会により健康志向食材の需要が増える可能性
1方で、政府による家計支援策や食費補助制度の拡充、または地方自治体による「地産地消」の推進がコスト抑制に寄与する可能性もあります。
まとめ
月間食料費は地域・世代・家族構成によって大きな差異を見せており、都市部では生活スタイルや可処分所得の高さから支出が増加。地方部では物価や自給的要素の影響で水準は低いものの、1部では急激な上昇も見られます。今後も生活実態や物価情勢と合わせて注視が必要です。




コメント