家計調査によると、2025年3月時点での女性用下着の世帯平均支出は393円。津市や相模原市では高く、鹿児島市や新潟市では非常に低い支出水準が見られる。地域差や世代構成、消費意識の違いが支出の差に表れている。物価上昇や機能性重視、EC利用の拡大など、今後の動向には世代別ニーズの分化と購買チャネルの変化が大きく関与するだろう。
女性用下着類の家計調査結果
女性用下着類の多い都市
女性用下着類の少ない都市
これまでの女性用下着類の推移
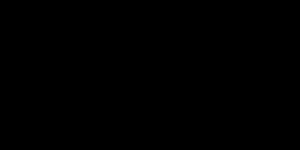
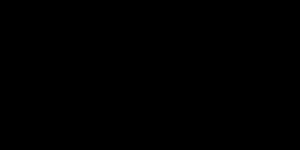
詳細なデータとグラフ
女性用下着類の下着類現状と今後
女性用下着は、消耗品でありつつも快適性・デザイン性・機能性が重視される生活必需品である。家計調査における「女性用下着類」支出は、単なる衣料品の購入金額にとどまらず、世帯の生活水準、ライフスタイル、価値観を反映する指標の1つである。ここでは、2008年から2025年3月までの傾向を踏まえつつ、都市別・世代別の支出特徴、背景要因、今後の見通しについて解説する。
長期的な支出の動向と背景
女性用下着類の支出は、2008年以降緩やかな下降傾向から、コロナ禍を経て2020年代に入り再び上昇に転じている。1因は価格の上昇であり、特に機能性や補整下着といった高単価商品の普及が支出額を押し上げている。
また、コロナ禍による在宅時間の増加で「ラクで機能的」な下着需要が1時的に高まり、以降も継続的に市場に影響を与えている。
支出の高い都市に見られる特徴
最新データによると、女性用下着の支出が高い都市トップ10には津市(799円)、相模原市(719円)、堺市(644円)などが並ぶ。これらの都市に共通する傾向は以下の通り。
-
都市部またはベッドタウンとしての性格:高所得層や働く女性が多い傾向にある。
-
購買力のある世代が多い:40代〜60代女性の比率が高く、高品質志向が表れやすい。
-
購買チャネルの多様性:百貨店や通販、ブランド専門店など選択肢が豊富で、結果として支出が高めに出やすい。
-
衛生意識・美意識の高さ:健康やボディラインの維持を重視する文化も背景にある。
例えば広島市は前年同期比+154.1%、高松市は+126.4%、松山市は+111.5%と大きく伸びており、いずれも地方中心都市でEC利用が定着しつつある点が共通している。
支出の低い都市とその背景
1方、支出が特に低いのは鹿児島市(126円)、新潟市(129円)、宮崎市(163円)など。これらの都市に共通する要因は以下のように分析できる。
-
高齢世帯の比率が高い:買い替え頻度が低下し、実質的な需要が減る。
-
購買チャネルが限定的:地方における選択肢の少なさやEC未利用層の存在。
-
節約志向の定着:下着に対する消費意識が「消耗品」から「節約対象」へと変化している地域性。
-
文化的価値観:過度な消費を避け、機能最優先の買い物スタイルが支出に反映されている可能性もある。
例えば北9州市(-65.53%)、青森市(-54.4%)といった都市では、家計圧迫により非優先支出が抑制されているとも考えられる。
世代間の違いと消費スタイル
世代別に見ると、20〜30代は「ファッションとしての下着」、40〜50代は「体型ケア」「健康目的」、60代以上は「機能性・快適性重視」といったように、価値観とともに支出の傾向が変わる。
若年層はSNSやインフルエンサーの影響を受けやすく、トレンドに敏感だが、可処分所得が少ないため購入頻度は抑えられる。1方、中高年層は購買力があり、「品質重視」で単価が高い下着を選ぶ傾向がある。
今後の予測と注目すべきトレンド
今後の女性用下着支出は以下のような要因で緩やかな上昇を見込む。
-
物価の上昇とブランド志向の強まり:機能性やデザインに価値を見出す層が増える。
-
EC(電子商取引)浸透の加速:地方都市でもEC利用が拡大し、支出金額に変化をもたらす可能性。
-
ジェンダー・エイジフリー化:年代や性別にとらわれない商品展開により、新たな顧客層の獲得が進む。
-
サブスク型サービスやセット販売:まとめ買いによる支出の変動が見られるようになる。
1方で、少子高齢化と地方過疎化により、支出の地域間格差はさらに広がる可能性もある。
まとめ――都市と世代で異なる“下着の経済学”
女性用下着支出には、単なる衣料費とは異なる多面的な意味がある。地域社会の年齢構成、経済状況、購買スタイル、価値観の変化が細やかに表れている。支出が高い都市ほど「選ぶ下着の質」が重視されており、低い都市では「必要最低限」が優先される傾向が見える。
今後、女性用下着市場は「価格と質のバランス」「ジェンダーレス志向」「オンライン購買」の3つの軸を中心に発展するだろう。都市ごとの支出額を眺めることで、見えてくるのは、まさに生活文化の地理的な多様性である。




コメント