二人以上世帯の「主食的調理品」支出は都市部で高く、特に東京都区部や前橋市、大阪市などで上位を占めています。高齢化や共働きの増加、中食文化の浸透が背景にあり、麺類・丼物・パン類などの需要が安定しています。一方で津市や盛岡市などでは支出が減少しており、物価高や自炊回帰、地域流通の違いが影響していると考えられます。今後も中食ニーズは高水準を維持しつつ、健康志向・価格意識によって内容が変化していくと予測されます。
主食的調理品の家計調査結果
主食的調理品の多い都市
主食的調理品の少ない都市
これまでの主食的調理品の推移
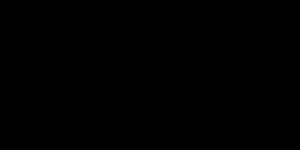
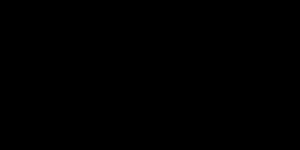
詳細なデータとグラフ
主食的調理品の調理品・外食現状と今後
主食的調理品とは、調理済み・半調理状態で提供される主食メニュー(丼、カレー、パスタ、パン類、弁当など)を指します。これらは家庭での調理の手間を省きつつ、食事としての満足感が得られるため、中食の中でも特に利用頻度が高いカテゴリーです。家計においては外食と自炊の中間として位置づけられ、生活スタイルの変化とともに支出額にも大きな影響が表れます。
都市別の支出動向と増減傾向
2025年3月時点の全国平均は月5690円。東京都区部は7525円とトップであり、続く前橋市(6894円)、川崎市(6887円)、大阪市(6828円)と、大都市や都市機能の集中する地域で高水準となっています。こうした都市では、共働き世帯比率が高く、調理時間の確保が難しいことが支出増の要因と考えられます。
注目すべきは、前橋市(+25.14%)や浜松市(+10.01%)、高知市(+12.16%)など地方中核都市でも支出が急増している点です。これらは地域のスーパーやコンビニによる中食商品の充実や、外食控えの代替需要が反映されていると推測されます。
1方、津市(3841円)、盛岡市(4079円)、京都市(4378円)などでは支出が低く、前年比で2桁の減少となっています。これらの地域では、物価上昇に対する節約志向の強さ、自炊回帰、地域による販売網の脆弱さなどが影響している可能性があります。
世帯構造・世代別の消費傾向
共働き世帯や子育て世帯では、主食的調理品は「手早く済ませられる主食」として需要が高く、弁当や丼、冷凍パスタなどの購入頻度が高まります。逆に、高齢世帯では食の細分化や栄養管理の意識が高くなり、ボリュームのある主食よりも副菜や軽食を選ぶ傾向があります。
また若年単身世帯では、外食を減らし、スーパーやコンビニの中食で済ませるケースが多く、手頃な価格と簡便性が支出額に反映されています。
価格上昇と品質変化 ― 調理品のコスト構造
物価の上昇は主食的調理品にも大きな影響を及ぼしています。原材料費、人件費、物流費が高騰し、内容量の縮小や価格の引き上げが進行しています。従来500円程度だった弁当類も600円台後半が増加しつつありますが、それでも外食より安価という位置づけが続き、需要の底堅さを保っています。
1方、健康志向や高齢化に応じた「低糖質ご飯」「雑穀米使用」「塩分控えめカレー」などのプレミアムラインも増加し、2極化が進んでいるのが現状です。
今後の動向と政策的課題
今後も主食的調理品の支出は、都市部を中心に1定の水準を保ちつつ、地方での格差が広がる可能性があります。中食は生活インフラの1部として定着しており、高齢化や共働きの常態化がその需要を支えます。
しかし、栄養バランスの偏りや食品添加物への懸念、容器ゴミの増加といった課題もあります。行政としては、地産地消型の中食支援や、健康調理品のガイドライン整備などを通じて、持続可能な中食文化の構築を後押しする必要があります。
まとめ
主食的調理品の家計支出は、都市化・ライフスタイル・物価変動・世代特性といった複数の要因によって形づくられており、地域によっては支出の増減幅が大きく異なっています。今後も家計における中食の重要性は増す1方で、価格・健康・地域支援の3点からのバランスをとる視点が不可欠となるでしょう。




コメント