2002年から2025年3月までの中古車支出の年齢別データを見ると、20代・30代前半の若年層の支出が急増しており、特に29歳以下の支出が22,760円と突出しています。一方で、50代を中心とする中高年層の支出は減少傾向です。本稿では、各年齢層の動向と背景を読み解きつつ、今後の中古車市場がどのように変化していくかを予測します。
年齢別の中古車
1世帯当りの月間支出
これまでの年齢別の推移
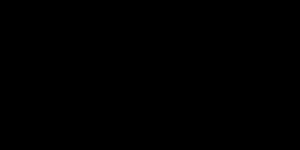
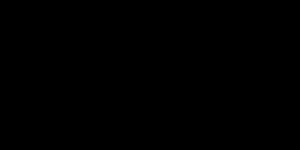
詳細なデータとグラフ
年齢別の現状と今後
中古車支出の年齢別平均は2025年3月時点で5,284円。これを大きく上回るのが29歳以下(22,760円)と34歳以下(19,460円)であり、若年層の中古車支出が際立って増加しています。特に前年同期比で+2184%という異常な伸びを見せた34歳以下の層は、2020年代以降の消費スタイルの変化を強く反映しています。
1方、かつて中古車需要の中心であった50代前後の層は、45~54歳が4,546円、50~54歳で5,597円と水準は高いものの、前年比で-42~43%と急減しています。高齢層(65~74歳)では増減が交錯しており、再び支出を増やす兆しも見られます。
若年層の中古車支出が急増した背景
新車価格高騰と若年層の現実的選択肢
新車価格の上昇により、若年層が「最初の車」として中古車を選ぶ傾向が強まっています。コロナ禍以降、通勤・移動の自立が必要になった若者が地方移住やリモートワーク定着の中で車を必要とし、中古車を手にするようになったと考えられます。
サブスクリプションやカーシェアを超える「所有」の回帰
都市部ではカーシェアが主流化していましたが、地方では依然として「所有」が重要であり、低価格で手に入る中古車に人気が集まりました。また「中古でもデザインが良ければ良い」といった実利重視の価値観が強くなっています。
支出増は維持費込みのライフスタイル転換
若年層の支出急増は、単なる購入ではなく維持費や改造費、メンテナンスへの支出も含まれる可能性が高く、生活の中で中古車の存在が大きくなっていることを示しています。
中高年層の支出減少の要因と意味
「手放し世代」への移行
50代~60代は子育て期を過ぎ、車の必要性が減少する時期でもあります。健康上の理由や都市部への移住などで車を手放す世帯も増えており、特に都市近郊に住む高所得層ほどこの傾向が顕著です。
車検・整備・保険費用の負担感
加齢によって収入が年金中心になる世帯では、維持費へのコスト意識が強まり、中古車を買い替えるよりも現有車を長く使う姿勢が目立ちます。
シニア層の再増加傾向とその背景
1部の高齢層(65~69歳、65~74歳)は前年比+79~98%と支出が再増加しています。これは、都市部の高齢者が再び車を使うようになったというより、地方在住のシニアが移動の必要性から中古車を新たに購入した結果と考えられます。
また、退職後に「セカンドライフ用の趣味車」や「軽トラ需要」などで、中古車を購入する例も見られ、支出に幅が出ています。
今後の年齢別中古車市場の展望
若年層:今後も堅調な支出が続く
エントリーユーザーとしての若者層は、今後もサブスクリプション的な使い方(数年で乗り換え)をしながら中古車市場に定着していくと見られます。
中高年層:2極化する支出
50~60代では、「維持継続派」と「完全手放し派」に2分される可能性があります。将来的には、事故リスクや免許返納制度の強化などにより、保有者数はさらに減少する見込みです。
シニア層:生活維持としての再取得が続く
地方在住高齢者にとって中古車は生活必需品であり、1定の支出は続くと予測されます。ただし、電動車・小型モビリティへの移行が進めば、支出形態自体が変化するでしょう。
まとめ:年齢ごとの役割が分かれる中古車市場
中古車の支出構造は、単なる収入や年齢に比例しない複雑な様相を呈してきています。若年層が経済合理性を重視して積極的に購入する1方、中高年層は用途や必要性で大きく行動が分かれており、市場は多層的に進化しています。政策的には高齢者の運転支援、若年層への保険料軽減策などが今後の焦点となるでしょう。




コメント