日本の自動車整備費は世帯人数や就業者数により大きく異なり、特に5人以上の大家族や就業者が多い世帯で支出が高くなっています。2025年3月時点の平均は5143円で、5人世帯は7329円と突出しています。家族数が多いほど車両保有台数や使用頻度が高くなり、結果として整備費も上昇。一方、就業者のいない世帯は支出が減少しており、今後も少子高齢化や車離れが進む中、支出構造に変化が見込まれます。
世帯別の自動車整備費
1世帯当りの月間支出
これまでの世帯別の推移
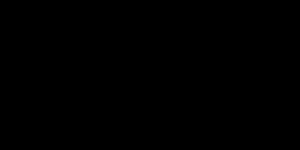
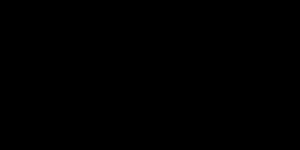
詳細なデータとグラフ
世帯別の現状と今後
日本における自動車整備費の世帯別支出は、長期にわたり社会構造やライフスタイルの変化とともに推移してきました。2025年3月時点でのデータによると、1世帯あたりの平均整備費は月間5143円。車を長く維持する傾向が強まるなかで、この支出は年々増加傾向にあります。本稿では、世帯構成別の整備費の違いとその背景、今後の見通しについて詳述します。
世帯構成別の整備費支出の現状
最新データによると、以下のように支出額に大きな差があります。
| 世帯構成 | 月間整備費 | 前年同期比増加率 |
|---|---|---|
| 世帯5人 | 7329円 | +88.6% |
| 世帯6人以上 | 6951円 | +21.31% |
| 就業者3人以上 | 5594円 | +8.579% |
| 就業者2人 | 5044円 | +16.71% |
| 世帯4人 | 4889円 | +12.99% |
| 就業者1人 | 4443円 | +17.32% |
| 世帯3人 | 4401円 | +9.587% |
| 世帯2人 | 4389円 | +2.189% |
| 就業者0人 | 3694円 | -9.924% |
最も支出が多いのは5人世帯で、約7300円。前年比+88.6%という急増ぶりからも、自動車依存が強くなっていることがうかがえます。
大家族ほど高くなる整備費の理由
複数台所有の傾向
世帯人数が多くなると通勤・通学・買い物など用途が多様化し、1世帯あたりの自動車保有台数が増えます。たとえば、親が通勤用・子が大学通学用といった構成で2台以上の車を所有するケースが1般的です。
使用頻度の高さ
人数が多い世帯では自動車の使用頻度が上がることで、タイヤ・オイル・バッテリーといった消耗品の交換サイクルが短くなり、整備費も増加します。
就業者数と支出の相関関係
就業者が多い世帯も、出勤や職場間移動に自家用車を活用するため整備費が高くなる傾向にあります。特に地方においては公共交通機関の代替手段として車の役割が大きく、働く世代を中心に車の維持コストが家計に占める割合が増しています。
整備費が減少している世帯の特徴
就業者0人の世帯(多くは高齢者世帯や非労働世帯)では整備費が3694円と低く、前年から約10%も減少しています。これは以下の要因が考えられます。
-
運転機会の減少(高齢により免許返納など)
-
車の買い替えを控え、最小限の整備で維持
-
外出頻度そのものの低下
今後の展望と課題
高齢化による支出の2極化
今後は、高齢者による車の非使用化(免許返納等)と、大家族・働き盛り世代の複数台所有化によって、整備費支出が2極化する可能性があります。
整備費の高騰リスク
物価上昇、人手不足、部品価格の上昇などにより、整備費はさらに高騰する可能性があります。特に2024~2025年の間にも10~15%の上昇が見込まれる地域も出てくるでしょう。
政策的対応の必要性
-
高齢者向けに車両整備費への補助や点検支援制度の導入
-
家族向け世帯に対する維持費軽減の支援制度
-
地方部における公共交通代替策の強化
これらの政策が、整備費の負担を緩和する鍵となるでしょう。
まとめ
自動車整備費は世帯構成に強く影響され、特に大家族や就業者が多い家庭では支出が急増しています。1方、高齢者世帯では減少傾向にあります。少子高齢化と都市構造の変化が進む中で、自動車整備費の家計に占める位置づけはますます注目される存在となっており、政策と家庭レベルの両方で対応が求められる時代に入っています。




コメント