日本の挙式・披露宴費用は世帯構成や就業状況で大きく異なり、就業者2人や少人数世帯では支出が急増しています。背景にはコロナ禍後の反動や価値観の多様化があります。一方で、非就業や多人数世帯では経済的制約などから支出が大幅に減少。今後は、経済的余裕のある層とそれ以外の層で支出が二極化し、簡素化と豪華化の両極端が進む見通しです。
世帯別の挙式・披露宴費用
1世帯当りの月間支出
これまでの世帯別の推移
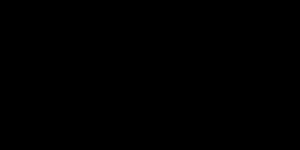
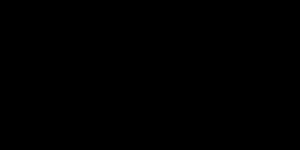
詳細なデータとグラフ
世帯別の現状と今後
物価の上昇が続く中、結婚関連支出にも新たな傾向が表れています。総務省の家計調査によると、2002年から2025年3月までの長期的データの中で、最新の世帯別挙式・披露宴費用の月間平均は321円となっています。この金額は、年間支出ではなく、統計上の「世帯あたり平均的な月次費用」を示しており、結婚式を挙げる世帯と挙げない世帯を平均化した結果です。
世帯別支出の内訳 ― 高所得層と小規模世帯の支出増
使用額の多い順で見ると、もっとも高額だったのは「就業者2人」の世帯で921円、次いで「世帯2人」が797円でした。これらの世帯は共働きの若年夫婦やDINKs(子どもを持たない夫婦)などが想定され、経済的な余裕から、式場や披露宴への投資が活発と考えられます。
さらに前年同期比で見ると、就業者2人は+163.9%、世帯2人は+146%と大幅に増加しており、これはコロナ禍明けによる結婚式の「リベンジ需要」や、挙式の形式が自由化したことで選択肢が広がり、支出が拡大していることを示しています。
支出が少ない世帯 ― 多人数・非就業世帯の低調
1方で、「就業者0人」(60円)、「世帯3人」(53円)、「世帯5人」(52円)、「就業者3人以上」(39円)といった世帯では、支出が極端に低く、前年からも大幅に減少しています。たとえば、「世帯5人」は前年比で-94.09%、「就業者3人以上」は-95.95%と急減しています。
これには複数の要因が考えられます。まず、子どもがいる世帯や3世代同居などでは、結婚適齢期の子世代がまだ結婚していない可能性があります。また、経済的な理由から結婚式を簡略化する傾向も見られ、フォトウェディングや家族のみの会食に留めるケースが増えています。
これまでの動向と時代背景
長期的に見ると、2000年代初頭には従来型の豪華な披露宴が1般的でしたが、2010年代に入ると「自分らしい結婚式」や「スモールウェディング」志向が強まり、費用を抑えるカップルが増えました。また、少子化・晩婚化・非婚化の進展により、挙式を行わない層も拡大しています。
1方で、2020~2022年のコロナ禍では結婚式の延期・中止が相次ぎました。その反動として2023年以降に「挙げ直し」や「後撮り」の需要が回復し、支出額の1部が跳ね返って上昇していると考えられます。
今後の予測 ― 2極化と多様化の加速
今後、挙式・披露宴にかかる支出は「2極化」が進むと予測されます。すなわち、経済的に余裕のある層はハイグレードな式を選び、1方で多くの世帯では簡素化・オンライン化・写真婚などで支出を抑える方向に進むでしょう。
特に注目すべきは「共働き夫婦」や「子なし世帯」による支出の増加です。彼らは自分のために消費できる可処分所得が高く、結婚式も自己実現の場として重視する傾向にあります。
1方で、子育て中や非就業世帯では、生活費の圧迫により、結婚式は後回し、もしくは行わないという判断が主流になる可能性があります。




コメント