家計調査によると、2025年3月時点の全国平均ガス代は6,999円。京都市や新潟市などでは1万円を超える一方、福井市や金沢市では3,000円台と都市間格差が大きい。増減率にも差があり、青森市や高松市では急上昇が見られる。過去20年の推移から見える供給インフラやエネルギー政策の違い、世代間の使用傾向、今後の再生可能エネルギーへの転換も視野に入れた解説を行う。
ガス代の家計調査結果
ガス代の多い都市
ガス代の少ない都市
これまでのガス代の推移
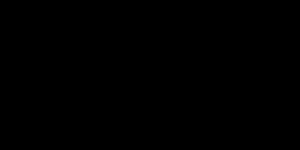
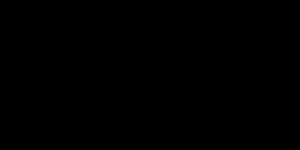
詳細なデータとグラフ
ガス代の現状と今後
2000年代初頭、都市ガスやLPガス料金は比較的安定していたが、2008年の原油価格高騰や為替変動、東日本大震災後のエネルギー構成の変化により、ガス代も大きく変動してきた。2020年以降は、ウクライナ情勢や円安の影響も加わり、都市ガス料金の上昇圧力が強まった。
2025年3月時点の全国平均は6,999円。これまでと比べてやや高止まりしているが、都市によって傾向が大きく異なる。
都市間の格差とその背景
最新データでガス代が高い都市(京都市13,560円、新潟市10,750円など)と低い都市(福井市3,153円、金沢市3,234円など)では、4倍近い開きがある。
この違いは主に以下の要因から生じている:
-
供給方式の違い:都市ガス(導管供給)とLPガス(ボンベ配送)では料金体系が異なる。都市ガスが普及している大都市圏では、導管整備費などが価格に反映されやすい。
-
地域の気候:寒冷地では冬季にガス使用量が増える。札幌市などは使用量が多いが、今回は前年比で-13.5%と減少しているのが特徴的。
-
自治体や事業者の価格政策:自治体ごとの競争環境や補助金政策も価格差に影響。
前年同期比の増減率から見る注目点
前年からの増減を見ると、青森市(+104.4%)、高松市(+80.91%)などの急増が目立つ。1方、福井市(-25.58%)、北9州市(-30.31%)などは大幅減。
これらの変動は以下の要因による可能性がある:
-
調達価格と為替の影響:地域別の契約先のガス会社による仕入れコストの差。
-
単月要因(異常気象など):冬が例年より寒かったか、暖かかったか。
-
料金改定のタイミング:年明けや新年度に料金見直しが行われるため、3月はその影響が反映されやすい。
世代別のガス使用傾向
若年世帯と高齢世帯ではガス使用の傾向が異なる。
-
若年勤労世帯は共働きが多く、在宅時間が短いため暖房や給湯の使用が限定的。IHなどの電化志向も強く、ガス使用量は少なめ。
-
高齢世帯は在宅時間が長く、ガス暖房・給湯を頻繁に使う傾向がある。都市によってはガスコンロの使用率も高く、月額使用量が大きい。
ただし、家計調査では「勤労者世帯」が対象なので、比較的中間年齢層(30代~50代)が多く、ガス代は地域要因の影響をより強く受けると考えられる。
今後のガス代の見通しと政策的課題
今後のガス代については、以下の要素が影響を与えると考えられる:
-
エネルギー政策の転換:カーボンニュートラルの流れで、再生可能エネルギーへのシフトが進むと、ガスの役割は調整電源的な位置づけとなり、価格が変動しやすくなる。
-
電化との競合:オール電化やヒートポンプ導入の進展により、ガスの家庭使用量は長期的には減少傾向が続く。
-
インフラ維持のコスト:人口減少とともに供給網の維持費を少人数で負担する構図となり、地方のガス料金がさらに上がる可能性がある。
1方で、災害時の復旧のしやすさや調理の利便性など、ガスには依然として支持がある。地域によっては補助金や自治体主導の価格安定化策が必要となる場面もあるだろう。
まとめ
ガス代の地域差は単なる価格の問題にとどまらず、インフラ、気候、政策、ライフスタイルと密接に関係している。全国平均で見れば1定の水準に収まっているが、都市別・世代別の実情を把握しなければ、真の家計負担は見えてこない。今後も定期的な家計調査の公表とともに、公共料金の地域格差是正への議論が求められる。




コメント